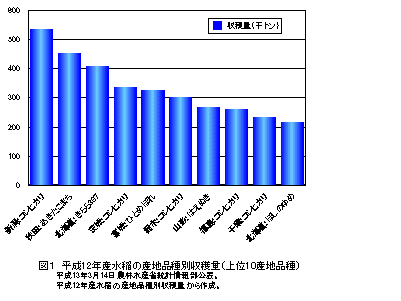図説:東北の稲作と冷害
お米の一大産地−東北−
平成12年産水稲の産地品種別収穫量(農林水産省統計情報部、平成13年3月14日公表)のデータを用いて、東北の稲作がわが国における米の生産量に占める重要度を紹介する。
お米の一大産地−東北−
東北の稲作は冷害との戦いといっても過言ではない。昭和6年、7年、9年、10年と続いた冷害は東北地域はもちろん、全国的に深刻な社会的影響を及ぼした。この冷害を契機に、近代的な冷害研究がわが国で一斉に始まった。これらの成果は着実に現れてきている。すなわち、明治、大正時代には東北地域の収量はきわめて低かったが、昭和25年頃になると、山形県の収量が全国第3位に躍進し、岩手県や宮城県の収量も全国平均に近づいてきた。そして平成2年になると、秋田、山形、青森の3県が全国の1から3位、トップ3を独占し、岩手、福島、宮城の3県もベスト10入りを果たした。現在、東北地域の稲作は作付面積で全国の約26%、玄米の生産量では約27%となり、一大産地といえる。この輝かしい米作りの躍進は、元青森県農業試験場長であり、数々の耐冷性品種を育成した田中稔さんの言葉をお借りると、生産者、行政普及関係者、研究者、民間など多方面の農業関係者の稲作改良にかけた情熱と努力、そして関係者の相互交流の結晶であるといえる。これら関係者は東北の気象条件そのものを変えたのではない。変えたのは稲作技術なのである。
さて、東北の稲作の現状を平成12年産米のデータで概観する。図1に上位10産地品種の収穫量を示す。これら10産地品種の合計の収穫量は全国の収穫量の35.1%を占める。産地名をみると、北海道、東北の秋田・宮城・山形・福島、関東の茨城・栃木・千葉、そして北陸の新潟となっている。品種名でみると、北海道の「きらら397」「ほしのゆめ」、全国に広く作られている「コシヒカリ」、秋田の「あきたこまち」、宮城の「ひとめぼれ」、山形の「はえぬき」となる。
「きらら397」「ほしのゆめ」は北海道の収穫量のそれぞれ56%、29%を占める。
「コシヒカリ」はそれぞれの県の収穫量に対して、新潟では81%、茨城79%、栃木79%、福島58%、千葉67%を占める。
「あきたこまち」は秋田県の収穫量の82%を占める。
「ひとめぼれ」は宮城県の収穫量の71%を占める。
「はえぬき」は山形県の収穫量の60%を占める。
なお、上位10産地品種の収穫量が全国の収穫量に占める割合は図2の通りである。
もう一つ注目すべきは、日本海側の秋田、山形と新潟の3県を除くと、北海道、東北、関東のこれら産地は冷害の危険度の高い地域といえる。したがって、冷害になると、これら産地の収穫量が減り、わが国の米の需給が大きく影響されるのである。