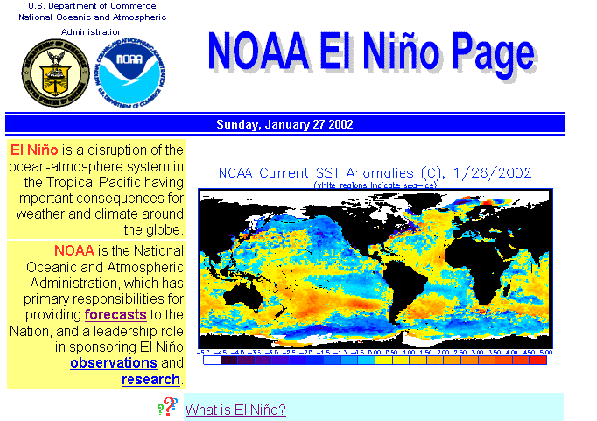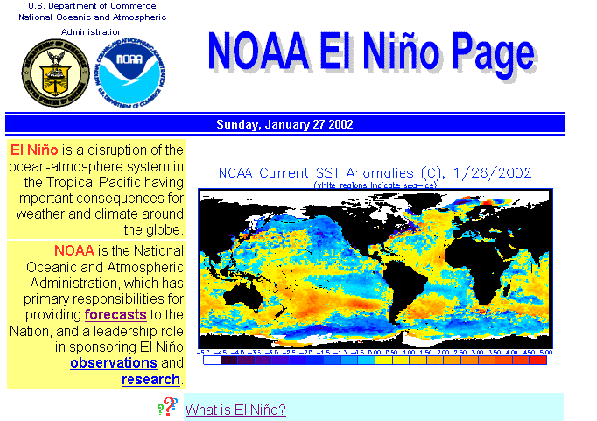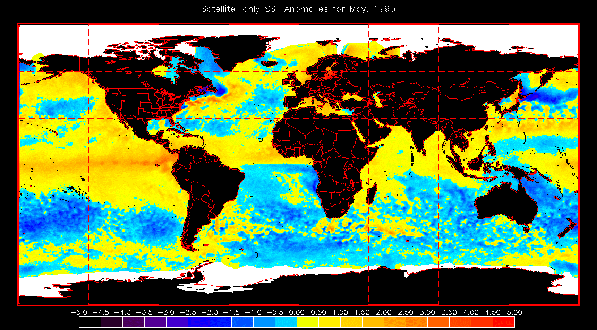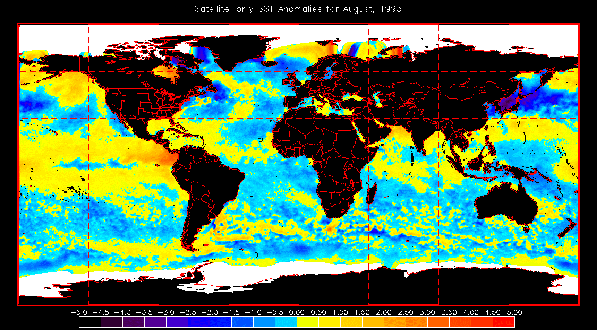図説:東北の稲作と冷害
エルニーニョ現象を監視する(衛星観測)
エルニーニョ現象は太平洋赤道域の海水温の状態変化に現れる。気象衛星のデータを用いて、全球の海面水温の偏差図を作成、公開するホームページを紹介する。
気象衛星NOAAによる観測データを基に全球の海面水温の偏差図を提供している米国海洋大気庁のエルニーニョ・ホームページ(http://www.elnino.noaa.gov/ 下図)を紹介する。
このページは、全球の海域の海面水温偏差図を気象衛星NOAAの観測データから週に2回(日本では水曜日と日曜日)作成し、更新している。また、1984年〜1998年までの月別偏差図も公表されている。ただし、1991年〜1992年のデータはピナツボ火山の噴火により大気中のアエロゾルが増えたために、欠測となっている。図では、赤の程度が強くなるほど、海面水温は平年より高く、反対に青の程度が強くなるほど、海面水温が平年より低いことをそれぞれ示す。白の部分は海面が氷で覆われていることを示す。
次に、1993年の5月と8月の月平均海面水温偏差図を図1と2に示す。同年は春からエルニーニョ現象が始まり、異常気象が世界的な規模で発生し、わが国では冷夏となり、大冷害となった。
5月の偏差図では、太平洋赤道域は広範囲で平年よりかなり高く、日本列島周辺の中緯度域の海面水温が平年より低かった。8月の偏差図では、太平洋赤道域の海面水温の正偏差程度は小さくなり、日本列島周辺海域の海面水温が平年よりかなり低かったことが分かる。
エルニーニョ現象が発生すると、わが国では冷夏になる確率が比較的高い。太平洋赤道域の大気と海洋の動向は、先の気象を予測するための重要な情報であるといえる。
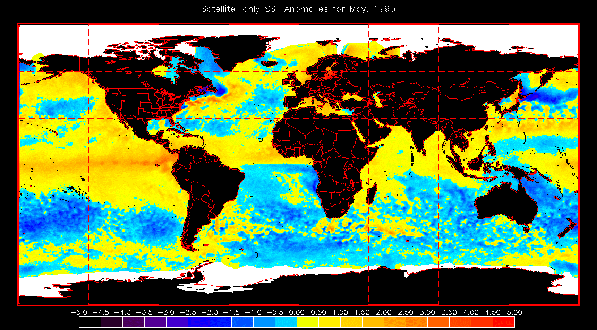
図1 1993年5月の月平均海面水温偏差図
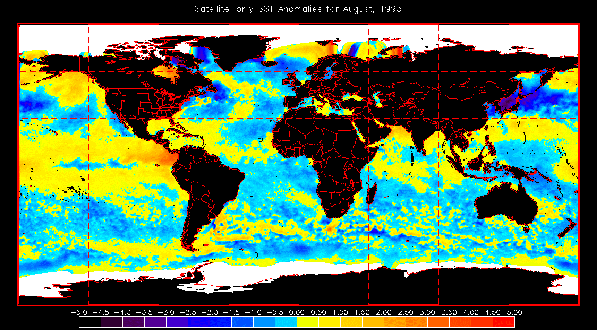
図2 1993年8月の月平均海面水温偏差図



reigai@ml.affrc.go.jp