図説:東北の稲作と冷害
主要品種の耐冷性
現在東北地域で作付されている品種の耐冷性ランキングと耐冷性育種の概要を説明する。
主要品種の耐冷性
耐冷性育種が大きく発展した理由は、耐冷性の精度の高い検定法「恒温深水法」の開発にある。この方法に基づく東北地域の主要品種の耐冷性ランキングは図の通りである。
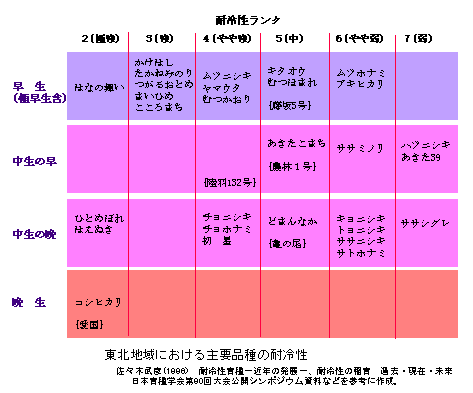 恒温深水法は冷水掛け流し方式により、大量の材料(系統・品種)を簡便に検定することができる。
恒温深水法は冷水掛け流し方式により、大量の材料(系統・品種)を簡便に検定することができる。
宮城県古川農業試験場が開発したこの方法は、稲の幼穂を一定の温度で処理するために、水温は地下水の混入により19度一定に保ち、水深は20cm以上に維持し、水温差が生じないように用水を強制循環する圃場を利用する。この方法では、1品種・系統3株程度で検定できるので、5アールの面積で約4千品種・系統の検定が可能となった。この圃場で出穂30日前頃から出穂まで水温19度で処理すると、不稔の発生割合は再現性も高く、現地で発生する不稔割合との相関も高いことが確認され、耐冷性の検定に広く利用されるようになった。
この検定法で「極強」と「強」の上位2ランクに入る品種を系譜別に整理すると、明治時代の品種である「愛国」と「神力」の子孫が3分の2以上を占めることが分かった。「愛国」の子孫には、農林8号を経て農林22号から「コシヒカリ」へと続く代表的な良質・良食味品種の系譜が辿れる。一方、耐冷性の最強級の系譜である「神力」の子孫では、東北地域で普及した品種は多くない。
耐冷性品種は品質や多収性などの実用形質も同時に優れていなければ実際には普及しがたい。耐冷性とこれら実用形質との間には負の相関関係があって、両立させる育種は難しいと言われてきた。しかし、1980年冷害で被害の少なかった「コシヒカリ」の耐冷性が極強であることが確認され、耐冷性育種の展望は急に開けた。1991年に育成された「ひとめぼれ」は「コシヒカリ」の耐冷性を利用して、耐冷性極強で品質・食味の極めて良い品種の育成が可能なことを実証したものである。
「ひとめぼれ」の耐冷性は、穂ばらみ期の平均気温19度にほぼ耐える程度である。平成5年の冷夏では古川市で「ひとめぼれ」に50%前後の不稔が発生した。その時の平均気温は18.5度であった。この0.5度の差で生じる不稔割合の差は40%近くになる。この差の克服が平成5年の冷夏が提起した今後の耐冷性育種の課題といわれる。
(参考資料:佐々木武彦(1996) 耐冷性育種−近年の発展−。耐冷性の稲育種 過去・現在・未来。日本育種学会第90回大会公開シンポジウム資料。5〜8頁。)
 ホームへ
ホームへ
 目次へ
目次へ
 ご意見をどうぞ
ご意見をどうぞ
reigai@ml.affrc.go.jp
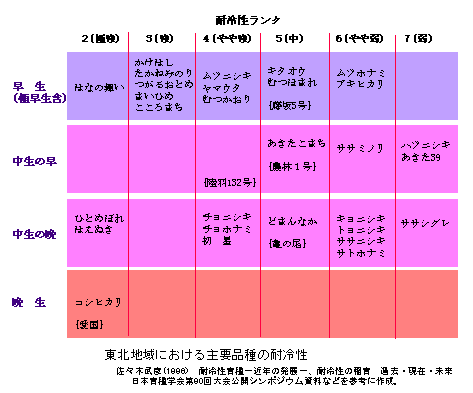 恒温深水法は冷水掛け流し方式により、大量の材料(系統・品種)を簡便に検定することができる。
恒温深水法は冷水掛け流し方式により、大量の材料(系統・品種)を簡便に検定することができる。