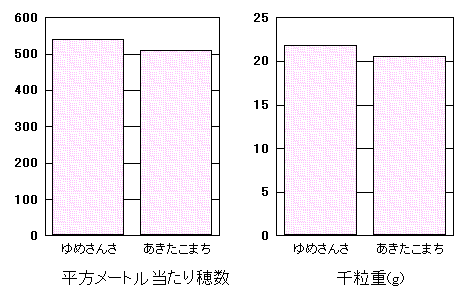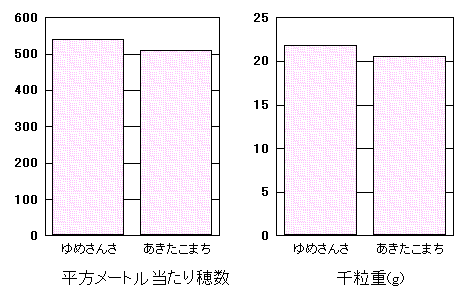図説:東北の稲作と冷害
品種解説:「ゆめさんさ」
本品種の障害型耐冷性は「あきたこまち」並みの“中”である。名前の意味は、“『ゆめ』または『さんさ』というニックネームで広く親しまれるお米でありたいという岩手の願いが込められていること”を表現する。
品種解説:「ゆめさんさ」
1.来歴の概要
「初星」を母とし、「庄内32号」(のちの「はなの舞」)を父として、1985年に岩手県立農業試験場で人工交配された。1991年に「岩手36号」の系統名が付けられ、1995年に「ゆめさんさ」として登録された。
2.形態的特性
・ 稈 長:「ササニシキ」よりやや長く、「あきたこまち」よりやや短い。
・ 穂 長:「あきたこまち」よりやや短い。
・ 穂 数:「ササニシキ」並みかやや少なく、「あきたこまち」より多い。“偏穂数型”のうるち種である(下図参照)。
・ 粒 大:粒厚は厚い。
・ 千粒重:「あきたこまち」「チヨホナミ」より大きい(下図参照)。
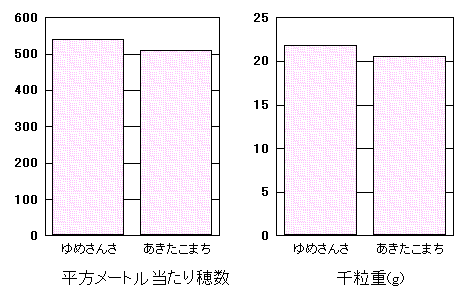
3.生態的特性
・ 出穂期:「チヨホナミ」並みである。
・ 成熟期:「あきたこまち」よりやや早い。育成地では“中生の早”である。
・ 収量性:「あきたこまち」並みかやや高い。
・ 耐倒伏性:「あきたこまち」より強く、「チヨホナミ」とほぼ同等である。
・ 葉いもち抵抗性:「ササニシキ」より強く、「あきたこまち」並みの“やや弱”である。
・ 穂いもち抵抗性:「ササニシキ」より強く、「あきたこまち」並みの“やや弱”である。
・ 耐冷性:“中”である。
・ 穂発芽性:「トドロキワセ」並みの“難”である。
| 特 性 | ゆめさんさ | あきたこまち |
|---|
| 耐冷性 | 中 | 中 |
|---|
| 耐倒伏性 | 中 | 中 |
|---|
| 葉いもち抵抗性 | やや弱 | やや弱 |
|---|
| 穂いもち抵抗性 | やや弱 | やや弱 |
|---|
| 穂発芽性 | 難 | 難 |
|---|
4.品質・食味特性
・年次により心白が発生することがある。
・ 玄米の外観品質は「あきたこまち」並みである。
・ 食味は「チヨホナミ」より良好、「あきたこまち」並みから良好で“上の中”である。
・ 白米中のタンパク質含量は「あきたこまち」より低く、「チヨホナミ」並みからやや低い。
・ アミロース含量は「あきたこまち」よりやや多いが、「ひとめぼれ」並みである。
5.適地等
・ 北上川中下流域および中南部沿岸地帯の「あきたこまち」および「チヨホナミ」栽培地帯に適する。
6. 岩手県での栽培法
・ 品種の熟期および耐冷性、品質などからみて、栽培適地はメッシュ気候図の好適区分の120〜200m(沿岸部は100〜200m)、適地区分の200m以下である。
・ 障害型耐冷性が「あきたこまち」並みの“中”なので、標高200m以上では栽培しない。また、登熟期が高温の年に標高100m以下で栽培した場合、特に心白粒の発生する割合が高まるので適地での栽培を厳守する。
7. 栽培上の注意点
1) 種子の休眠性が強いため、催芽前の浸種を十分に行う。
2) 平方メートル当たり籾数が減少すると千粒重が大きくなり、心白の発生する割合が高まるので、品質を高めるためには必要穂数を確保するよう基準にそった栽培を行う。
3) 平方メートル当たり籾数を確保するためには、基肥窒素を「あきたこまち」より成分量で1kg/10a程度増やす(県南分場では6kg/10aとする)。
最高分げつ期の茎数の指標は次の通り。
平方メートル当たり最高分げつ期茎数 680-800本、期待される穂数 510-550本。
4) いもち耐病性は「ササニシキ」にやや優るが、「あきたこまち」程度のため、「あきたこまち」に準じた適期防除に努める。また、耐冷性は「あきたこまち」並みでやや弱いので、減数分裂期低温時には深水管理を徹底する。
5) 追肥の重点時期は幼穂形成期とし、通常の生育では窒素成分量で2kg/10a以内を基本とする。減数分裂期以降の窒素の追肥は、白米中のタンパク質含有率を上げ食味を低下させるので避ける。また、過度の施肥は倒伏を助長させるので避ける。
栄養診断(幼穂形成期)の指標は次の通り。
・ 平方メートル当たり稲体乾物重:400-500g
・ 稲体窒素濃度:1.7-2.2%
・ 平方メートル当たり窒素吸収量:7.0-8.5g
・ カラースケール(単葉):3.9-4.6
・ SPAD葉色計:34-40
6)「あきたこまち」に比較すると登熟が早い傾向にある。このため、刈り取りは出穂後の登熟積算気温900-1,050度を目安として実際の登熟状況も観察して適期に行う。
7)生産および品質が安定する収量構成要素の指標は次の通りで、収量は550-600kg/10a(1.9mm篩目)を期待できる。
・ 平方メートル当たり穂数:510-550本
・ 1穂籾数:54-60粒
・ 平方メートル当たり籾数:30,000-33,000
・ 玄米千粒重:22.5g(1.9mm篩)
・ 登熟歩合:85%以上
・ 稈長:77-82cm
8)粒厚が厚い品種であるため、1.7mm篩では未熟粒割合が高くなり整粒を確保できない。そのため、基本技術である1.9mm篩の使用を徹底することにより未熟粒を除去する。
<名称選定の理由>
○ このお米のおいしさを、「ゆめさんさ」の語感が持つ優しさ・上品さ・明るさにマッチさせました。
○ 『ゆめ』は、宮沢賢治が思い描いた田園と風と光にみちあふれた夢の世界(イーハトーブ)にもつながります。
○ 『さんさ』は、岩手に踊り継がれてきた「さんさ踊り」に由来します。まだ、自然に恵まれた岩手の大地に燦燦とふり注ぐ太陽をも表しています。
○ このように『ゆめ・さんさ』は岩手のアイデンティティであることから、産地の期待を込めて夢が膨らむ『ゆめさんさ』と名付けられました。
○ 『ゆめ』または『さんさ』というニックネームで広く親しまれるお米でありたいという岩手の願いが込められています。
<参考資料>
・ 県が奨励する農作物奨励品種「岩手34号」「岩手36号」
・ 平成11年度岩手県稲作指導指針。
・ 東北農業試験場編「平成4年度東北農業研究成果情報」No.7
 ホームへ
ホームへ
 目次へ
目次へ
 ご意見をどうぞ
ご意見をどうぞ
reigai@ml.affrc.go.jp