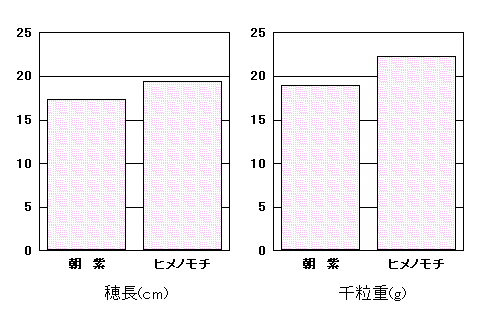図説:東北の稲作と冷害
品種解説:「朝 紫」
本品種の耐冷性は「ヒメノモチ」よりやや弱い。名前の意味は、“わが国初の紫黒米であり、今後の発展を祈念する気持ち”を表現する。
品種解説:「朝 紫」
1.来歴の概要
1984年に熱帯農業研究センター沖縄支所で「タツミモチ」と「BP-1」の人工交配が行われた後、交配種子が宮城県古川農業試験場に分譲され、1985年に同試験場において「タツミモチとBP-1の第一世代」を父、「中部糯57号(ココノエモチ)」を母として人工交配された。育成中の第六世代系統「東糯396号」が1988年に東北農業試験場に分譲された。1993年に「奥羽糯349号」の地方番号が付けられ、1996年に水稲農林糯349号として登録された。
2.形態的特性
・ 草 丈:分げつ期では「ヒメノモチ」よりやや長く、分げつ性はやや低い。
・ 稈 長:「ヒメノモチ」並みの中長稈である。
・ 穂 長:「ヒメノモチ」より短い(下図参照)。
・ 穂 数:「ヒメノモチ」並みである。
・ 粒大・粒重:「ヒメノモチ」より小さい(下図参照)。
・ 玄 米:果皮がアントシアン系の濃い紫色を呈し、真っ黒にみえる。完全に搗精すると一般の糯品種と同様の白色になる。
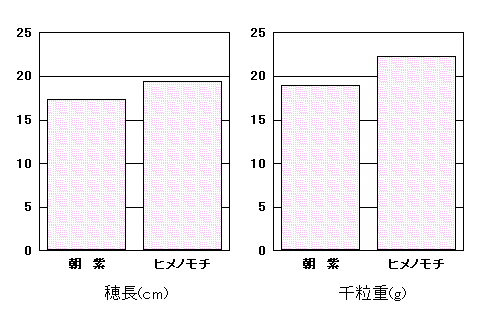
3.生態的特性
・ 出穂期・成熟期:「ヒメノモチ」と同程度で、早生の晩である。
・ 収 量:「ヒメノモチ」より10〜20%低い。
・ 耐倒伏性:「ヒメノモチ」並みかやや強い。
・ 葉いもち抵抗性:「トヨニシキ」並みの“強”である。
・ 穂いもち抵抗性:「ササニシキ」並みの“弱”である。
・ 耐冷性:「ヒメノモチ」よりやや弱い。
・ 穂発芽性:“中”
| 特 性 | 朝 紫 | ヒメノモチ |
|---|
| 耐冷性 | やや弱 | 中 |
|---|
| 耐倒伏性 | 中 | やや弱 |
|---|
| 葉いもち抵抗性 | 強 | 強 |
|---|
| 穂いもち抵抗性 | 弱 | 強 |
|---|
| 穂発芽性 | 中 | 易 |
|---|
4.品質・食味特性
・ 餅の食味は「ヒメノモチ」に比べ粘りがやや弱いが、腰の強さ、舌触りは大差なく、総合的にみて、「ヒメノモチ」並みかやや劣る程度である。
・ 7〜8分搗きにして、わずかに紫色の果皮を残した米を炊いたり、蒸したりすると炊飯米全体が紫色になる。その色の濃淡は搗精の程度による。
・ 一般の白米に本品種の玄米を混合して炊飯しても、炊飯米全体が赤飯のような赤紫色を呈する。
・ 完全搗精した場合の米飯の物理性などは一般の糯品種と比べ大差ない。高温登熟した場合の色素含量は明らかに低い。玄米のビタミン類は一般品種と大差なく、カルシウムとカリウムの含量が高い。
5.適地等
・ 東北地方中南部の平坦地に適する。
6.栽培上の注意
・ 耐冷性がやや弱いので、冷害の発生しやすい地帯での栽培は避ける。
・ 穂いもち抵抗性が「ササニシキ」と同程度に弱いので、穂いもちの防除に留意する。
・ 米が紫黒色なので、一般米に混入しないよう特に注意する。また、翌年一般品種を栽培する場合は、こぼれ種子の発芽、生育に注意し、適宜抜き取る。
・ 他家受精を通した玄米色の遺伝的拡散を防ぐため、採種圃場の付近や出穂期が同じ品種の隣では栽培しない。
<参考資料>
農林水産省農林水産技術会議事務局(平成8年8月):平成8年農林水産省育成農作物新品種(夏作物・園芸作物)。



reigai@ml.affrc.go.jp