図説:東北の稲作と冷害
障害不稔発生警戒のための平均気温指標
平成5年冷害の現場データに基づいて、出穂前30日の平均気温と障害不稔発生率との関係から、不稔発生を早期に警戒するための基準平均温度を設定した。その基準となる平均気温は、「むつほまれ」19.5度、「あきたこまち」20度、「ササニシキ」と「ひとめぼれ」20.5度。
障害不稔発生警戒のための平均気温指標
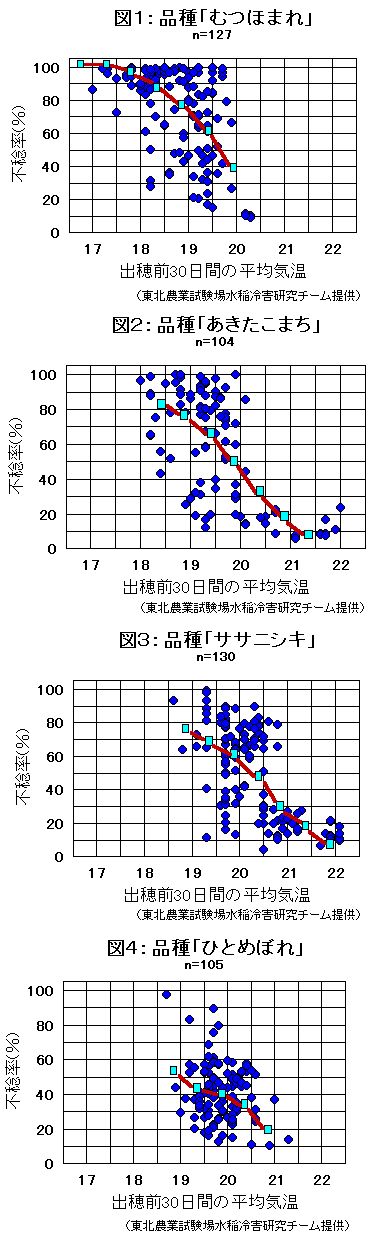 水稲冷温障害で最も被害の大きい障害不稔の発生を早期に予察することは最も重要である。この障害不稔は水稲の穂が形成される幼穂形成期(幼穂長2mmの頃)から出穂期に冷温に遭遇すると発生する。冷温に対して最も敏感な時期は出穂前11日頃の減数分裂期である。この障害不稔の発生を早期に予察するための指標はできないか。
水稲冷温障害で最も被害の大きい障害不稔の発生を早期に予察することは最も重要である。この障害不稔は水稲の穂が形成される幼穂形成期(幼穂長2mmの頃)から出穂期に冷温に遭遇すると発生する。冷温に対して最も敏感な時期は出穂前11日頃の減数分裂期である。この障害不稔の発生を早期に予察するための指標はできないか。
平成5年は、穂が形成される長期にわたり低温・日照不足が続き、障害不稔が多発したために大冷害になった。(平成5年冷害の実態参照)平成5年は冷害が予知されたため、管内の農業改良普及センターは被害実態を把握するために多数地点で品種別、出穂期別の不稔率の調査を実施した。その結果は各種冷害の記録としてとりまとめている。それら資料と試験研究機関が公表した同様のデータを用いて、近傍アメダス観測地点の出穂前30日間の平均気温を算出し、平均気温と不稔発生率の関係を検討した。
対象とした品種は太平洋側の主要品種である「むつほまれ(耐冷性中)」、「あきたこまち(同中)」、「ササニシキ(同やや弱)」、「ひとめぼれ(同極強)」の4つである。これら品種に障害不稔の発生が予知される場合は社会的に大きな問題となるからである。
品種別にみた出穂前30日間の平均気温と不稔率との関係は図1〜4の通りであった。図中の実線は散布の傾向を示す。
平均気温がある値以下になると、不稔率は平均気温が同じでも不稔率に大きな変異がみられる。その範囲は、「むつほまれ」18.5〜19.5度、「あきたこまち」19.0〜20.0度、「ササニシキ」と「ひとめぼれ」19.5〜20.5度であった。平均気温がこの範囲以下になると高い不稔率となった。
この散布のバラツキが大きくなる理由としては、アメダス設置地点周辺の環境、近傍の水田立地、栽培管理等の違いが反映されているものと考えられる。
このことから、早期警戒の監視業務において不稔発生を予察する指標として、幼穂形成期以降のアメダス平均気温の平均値を用いることができる。各品種の目安となる平均気温としては、「むつほまれ」19.5度、「あきたこまち」20度、「ササニシキ」と「ひとめぼれ」20.5度が適当であると判断される。ただし、平成5年の気象条件は100年に一度の頻度ともいわれ、他の予測手法(例えば減数分裂期の冷却量による不稔発生の推定等)を併用して監視することが必要である。



reigai@ml.affrc.go.jp
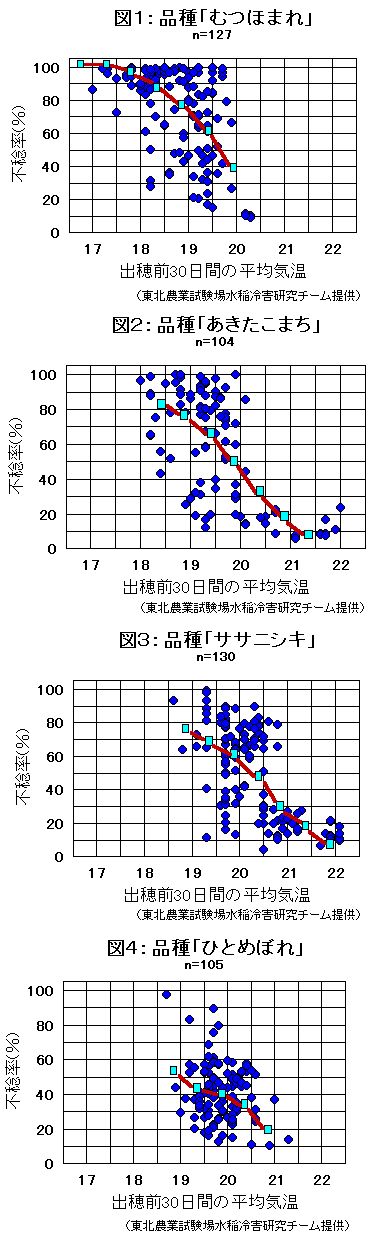 水稲冷温障害で最も被害の大きい障害不稔の発生を早期に予察することは最も重要である。この障害不稔は水稲の穂が形成される幼穂形成期(幼穂長2mmの頃)から出穂期に冷温に遭遇すると発生する。冷温に対して最も敏感な時期は出穂前11日頃の減数分裂期である。この障害不稔の発生を早期に予察するための指標はできないか。
水稲冷温障害で最も被害の大きい障害不稔の発生を早期に予察することは最も重要である。この障害不稔は水稲の穂が形成される幼穂形成期(幼穂長2mmの頃)から出穂期に冷温に遭遇すると発生する。冷温に対して最も敏感な時期は出穂前11日頃の減数分裂期である。この障害不稔の発生を早期に予察するための指標はできないか。