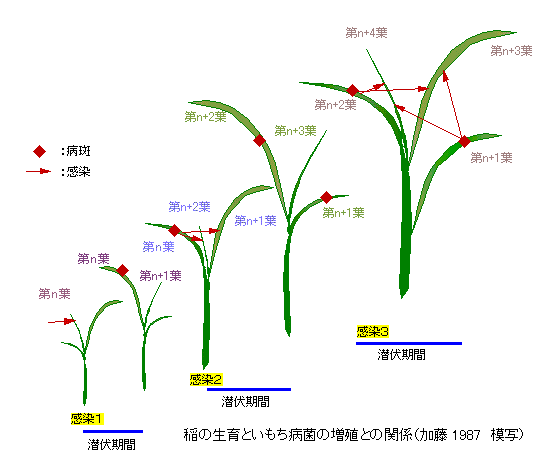図説:東北の稲作と冷害
いもち病菌の増殖過程
いもち病の発生は罹病苗や保菌苗から周辺に広がるのが一つの特徴である。感染と発病を4回程度繰り返すことで、広く蔓延していく増殖過程を解説する。
いもち病菌の増殖過程
本田における葉いもちの伝染源は、罹病苗と保菌苗の持ち込みと、被害わらや早期に発生した水田あるいは稲以外の罹病植物などから分生子の飛来によるものとがある。
前者の場合は、罹病苗や保菌苗を中心に周辺の株に次々と第二次伝染が起こり、発病中心株で症状が激しく、遠ざかるにつれて症状は軽くなる、「坪状発生」が起こる。
小林(1984)のモデル実験によると、その病斑拡大の様相は次のように説明されている。
- 株当たり1〜2個の病斑をもった伝染源から飛散した分生子による第2世代病斑は1平方メートルの範囲に及ぶ。
- 次に、そこから飛散した分生子による第3世代病斑は10平方メートルの範囲に及ぶ。
- そして、第4世代では圃場の全面に広がり、全株に病斑が形成される。
このように感染と発病を4回ほど繰り返すと、圃場の全面に広がるようになる。
加藤(1987)は上の葉いもち病斑の増加過程を稲の生育との関係で下図のように分かりやすく解説している。
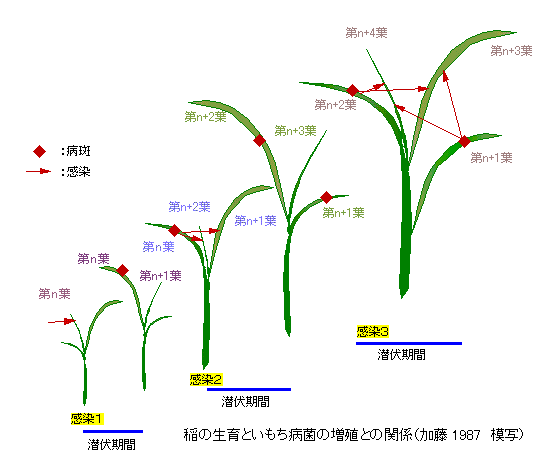 いもち病菌の増殖過程は次のような経路で起こる。
いもち病菌の増殖過程は次のような経路で起こる。
- 最もいもち病に罹りやすい展開中の第n葉に分生子が落下し、感染するとほぼ5日間の潜伏期間を経て発病する。(図中左2つの絵参照)
- その後4日間で病斑が拡大し分生子を形成し、その分生子が飛散して第n+1葉と第n+2葉に落下し、侵入・感染する。(左から3番目の絵参照)
- ある期間の潜伏期間を経て、第n+1葉と第n+2葉に発病し、その後病斑が拡大し分生子を形成する。それらが第n+3葉と第n+4葉に飛散・落下し、侵入・感染する。(左から4,5番目の絵参照)
このように、分げつ期に抽出中の葉の主な伝染源は2枚前に展開した葉の病斑上の分生子で、伸長期に入ると1枚前の展開した葉の病斑上の分生子となる。
穂いもちとの関係では、最も分生子形成能の高い病斑は出穂開始期では止葉の一枚下の葉に分布している。この葉は、出穂開始期には止葉葉節より高い位置にあり、抽出中の穂への分生子の落下には都合が良いといわれる。また、止葉葉節はいつまでも感染しやすく、そこにできた病斑上の分生子も穂いもちの伝染源として重要な役割を果たしている。
このようないもち病菌の増殖過程から、早期発見と早期防除が最も重要な技術であることが理解できる。
<参考資料>
○大畑貫一(1989)。稲の病害−診断・生態・防除−。全国農村教育協会。>
○山中 達・山口富夫(1987)。稲いもち病。養賢堂。>
○加藤 肇(1987)「発生生態−疫学」『稲いもち病』養賢堂。
○小林次郎(1984)「発生初期における葉いもちの疫学的研究」、秋田県農業試験場研究報告 26:1-84.



reigai@ml.affrc.go.jp