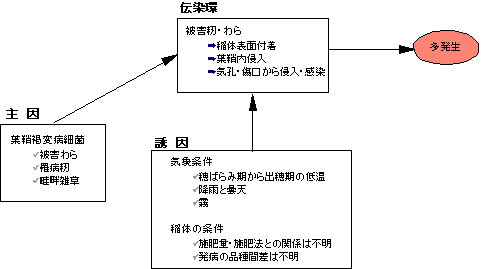図説:東北の稲作と冷害
葉鞘褐変病の主因と誘因
本病は冷害年に北海道で多発することが知られていたが、昭和51年の冷害時に東北地域でも発生が初めて認められたものである。本病細菌の生態や防除に関する研究は少なく、効果的な防除対策は確立されていない。
葉鞘褐変病の主因と誘因
葉鞘褐変病は北海道では古くから発生していたようで、特に冷害年に多発することから、生理障害と考えられていた。舟山・平野(1962)や谷井ら(1976)らの研究によって、細菌病の一つであることが判明した。発生は北海道に限られていたが、昭和51年の冷害時に、東北地域でも青森、岩手、宮城県を中心に本病あるいは類似症状が発生した。本病は一般に穂ばらみ期に発生する。はじめ止葉葉鞘に暗褐色水浸状の斑紋を生じ、拡大して大型病斑となる。穂は出すくみ、籾は一部あるいは全面が暗褐色ないし黒褐変する。罹病籾の玄米表面に褐色の斑紋が生じ、激しい場合は全体が褐変し茶米となる。
本病の主因と誘因との関係は下図の通りである。
主因は葉鞘褐変病細菌である。本細菌は被害籾やわらで越冬する。その後、本田の稲体に付着し、穂ばらみ期に至って発病に好適な低温条件にあうと、止葉葉鞘の裏面の気孔や傷口から侵入して感染する。
誘因としては、気温と最も密接に関係する。穂ばらみ期から出穂期にかけての低温が本病の発生に必要な条件である。低温によって出穂が遅れ、最も感染しやすい穂が止葉葉鞘内に長くあり、本病の増殖が促進される。また、穂ばらみ期から出穂期にかけての降雨や曇天、または霧は発病を助長するといわれている。
本病の発生は気象条件、特に低温によって大きく左右される。耕種的な施肥量、移植時期と被害との関係は年次や場所によって異なるため、効果的な耕種的防除対策は講じにくい。ただ、出穂のバラツキを少なくするような、夜間灌漑による水温の上昇を図るとともに、分げつ過多にならないような栽培管理が基本となる。
本病が発生しやすい北海道の『農作物病害虫防除基準・除草剤使用基準(平成11年2月)』によると、抗生物質の薬剤名「オキシテトラサイクリン・ストレプトマイシン」は"登録があり北海道で指導参考事項となっている薬剤"として掲げられている。また「カスガマイシン」は"登録はあるが指導参考事項となっていない薬剤"となっている。
(参考図書:大畑貫一(1989):稲の病害−診断・生態・防除−、全国農村教育協会)



reigai@ml.affrc.go.jp