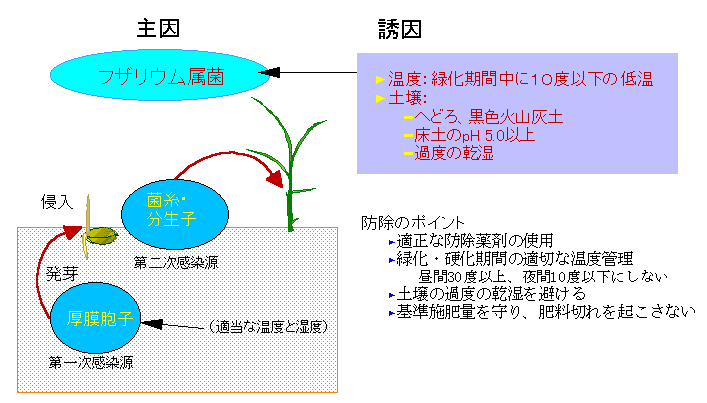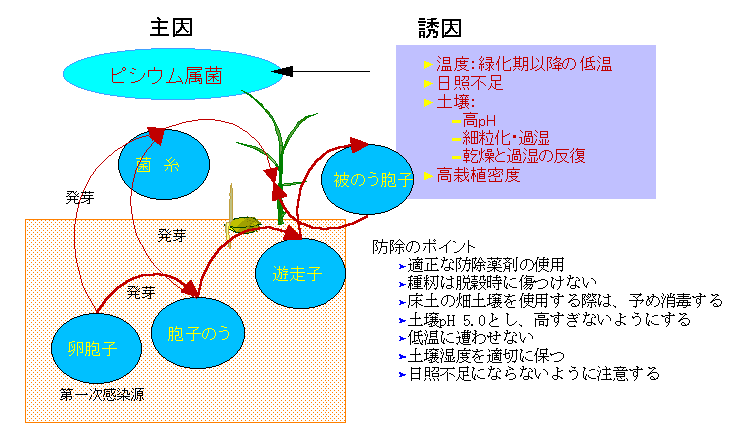図説:東北の稲作と冷害
苗立枯病
育苗期の主要病害である苗立枯病の代表的なものの診断・生態・防除を概説する。
苗立枯病
機械移植用箱育苗では、従来の苗代と異なり、床土面に湛水せず、播種密度が高く、高温・多湿条件下で出芽が行われる。このような環境下では従来の苗代でみられていたフザリウム属菌、ピシウム属菌のほかに、新たにリゾプス属菌、ムコール属菌、トリコデルマ属菌、リゾクトニア属菌、白絹病菌などによる苗立枯病が発生するようになった。これらの被害は一応克服されたが、ちょっとした油断や手抜きから被害を招くことがある。
箱育苗で発生する苗立枯病で被害が最も大きいのはリゾプス属菌によるもので、次いでフザリウム属菌、ピシウム属菌によるものである。トリコデルマ属菌による苗立枯病の発生は局地的であるが、いったん発生すると病勢の進展が速く被害が致命的となる。
1.フザリウム属菌による苗立枯病
これによる苗立枯病は東北地方を中心に、育苗期間の気温が低い地域で発生が多い。
種籾の発芽直後から発生する。根および苗の地際部が褐変腐敗し、苗の伸びは悪く、地上部は萎ちょうし、後に黄化して枯死する。局所的に発生し、ときに育苗箱全体に広がることがある。
罹病苗の地際部には白色あるいは紅色の粉状のカビが生えることが多い。
本病の伝染環、誘因ならびに防除のポイントは下図の通り。
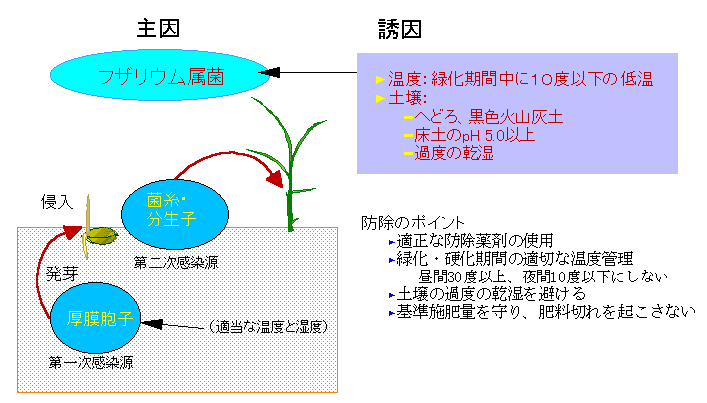
2.ピシウム属菌による苗立枯病
ムレ苗の主因はピシウム属菌で、低温、日照不足、床土の高pH、土壌の過湿、窒素不足等が誘因となる。
ピシウム属菌による苗立枯病の病徴には次の2つの型がある。すなわち、
1) 出芽後間もない幼芽が侵され、根は水浸状に褐変腐敗して苗は枯死する。「幼芽の立枯型」
2) 苗が2,3葉になってから急に萎ちょうし、後に枯死する。根は水浸状に褐変するが、出芽後まもなく発生する場合ほど顕著ではない。「萎ちょう・立枯型」
フザリウム属菌の場合のように、病患部が紫褐変したり、苗の地際部やまわりの土壌表面に白色ないし紅色の粉状のカビが生えることはない。
本病の伝染環、誘因ならびに防除のポイントは下図の通り。
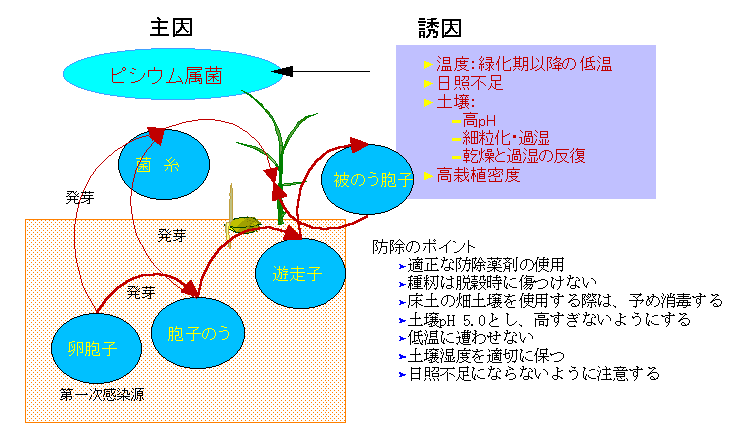
3.リゾプス属菌による苗立枯病
本病は生育がきわめて速く、いったん発生すると急速に蔓延し、その被害はフザリウム属菌やピシウム属菌によるものより大きい。
出芽時に種籾のまわり、あるいは床土面に白い綿毛状のカビが点々と生え、急速に繁殖して、出芽室から搬出する頃には、育苗箱全面を覆うほどになる。白いカビは後に灰色になる。種籾の出芽は悪く、出芽してもその後の生育は劣り、黄緑色に退色して苗は不揃いになる。根は短く、先端が異常に膨らんで伸長が止まり、後に褐変腐敗する。ひどい場合は枯死する。
中・成苗のように出芽後戸外で緑化、硬化を行う場合、床土表面には白いカビがみられないが、苗の生長が悪く不揃いになっている場合がしばしばある。このときに根のマット層の裏側や種籾のまわりにリゾプス属菌の白い菌糸が密生している。
本病の伝染環、誘因ならびに防除のポイントは下図の通り。

4.トリコデルマ属菌による苗立枯病
本病による苗立枯病の発生面積はリゾプス属菌等による苗立枯病に比べて少ないが、いったん発生すると被害が致命的となるので恐れられている。
はじめ床土の表面や種籾のまわりに白いカビが生え、しばらくするとカビは黄緑色から青緑色となる。床土表面からは見えなくても、種籾層に菌糸が蔓延している場合がある。激発すると、出芽前に種籾が腐敗し、出芽しても苗は黄化し、生育も悪くやがて枯死する。症状が軽い場合は、苗はやや黄化し、草丈は低く、不揃いになる。根は褐変して短くなり、根数も少ない。ふつう苗箱内ではパッチ状に発生する。
本病の特徴は床土表面や種籾のまわりに青緑色のカビが密生することである。これは病原菌の胞子塊である。
本病の伝染環、誘因ならびに防除のポイントは下図の通り。




reigai@ml.affrc.go.jp