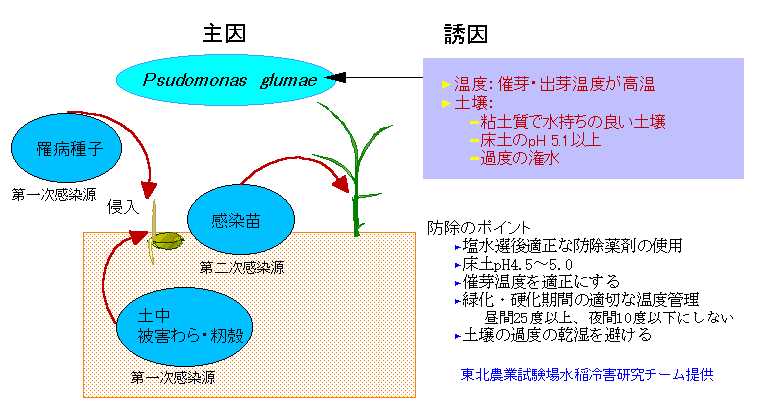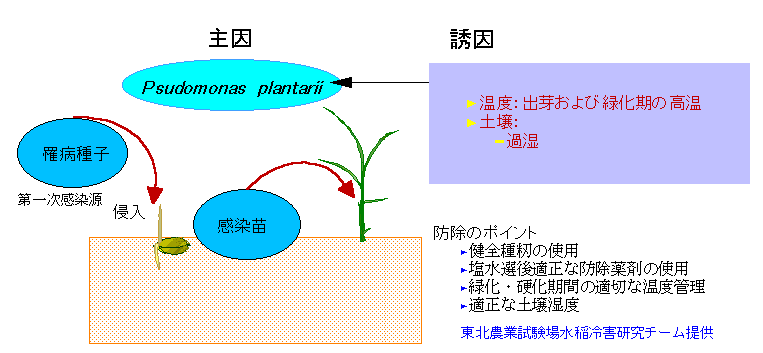図説:東北の稲作と冷害
細菌病
育苗期の主要病害である細菌病の代表的なものの診断・生態・防除を概説する。
細菌病
1.もみ枯細菌病
もみ枯細菌病で出芽時にひどく感染すると、幼芽は湾曲し、淡褐色ないし褐色になり、腐敗・枯死する。緑化から硬化期にかけて、生き残った苗の葉鞘は淡褐変ないし濃褐変し、芯葉は腐敗した葉鞘を破ってめじれながら抽出する。また、葉齢が進んでから感染した場合には葉鞘が褐変・腐敗し、芯葉は基部が腐敗して抜けやすくなるか、葉の基部が退色して白色になる。このような苗は褐変腐敗して、ついには枯死する。
症状が軽い場合には、葉鞘だけが褐変・腐敗し、生き残る苗もあるが、生育不揃いとなり移植にはたえられない。
普通育苗箱ではパッチ状に発生する。罹病した腐敗苗には悪臭がある。
箱育苗で発生する細菌病には本病のほかに、褐条病と苗立枯細菌病がある。褐条病では葉鞘に暗褐色水浸状の条班が現れる。苗立枯細菌病では、苗は褐変枯死しても抽出中の芯葉の基部が腐敗して抜けやすくなることはない。なた、苗立枯細菌病では末期には苗が赤茶けて枯死するのが特徴である。
本病の伝染環、誘因ならびに防除のポイントは下図の通り。
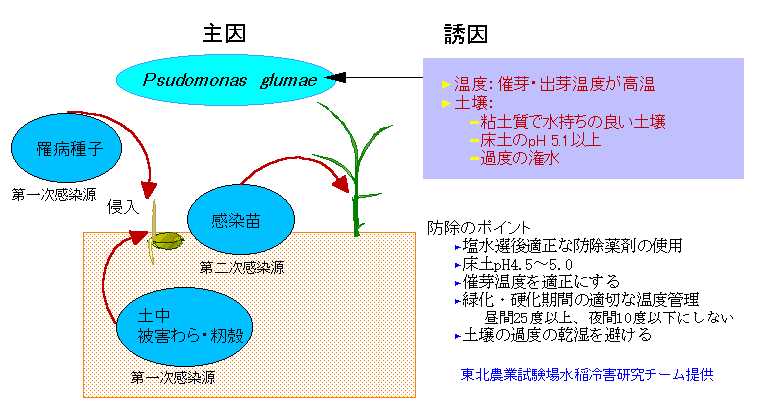
2.苗立枯細菌病
本病は最近千葉県下の箱育苗で発見された新しい細菌病である(1983年)。その後関東各地ならびに宮城、新潟などで発生が確認されているが、初期症状がもみ枯細菌病による苗腐敗症と似ており、現地では両者が混同されていることもあって被害の詳細は明らかでない。しかし、種子伝染するので今後警戒を要する病気である。
初期症状はもみ枯細菌病による苗腐敗症と似ており、第3葉基部にクロロシスが現れ、ついで第3葉から萎ちょうし始める。やがて罹病苗は赤茶けたようになって枯死するが、もみ枯細菌病のように苗が腐敗することはない。根の生育はきわめて悪い。ひどいときには育苗箱全体の苗が枯死する。
本病の場合苗の基部が腐敗しないので、もみ枯細菌病のように芯葉は容易に引き抜けない。
本病の伝染環、誘因ならびに防除のポイントは下図の通り。
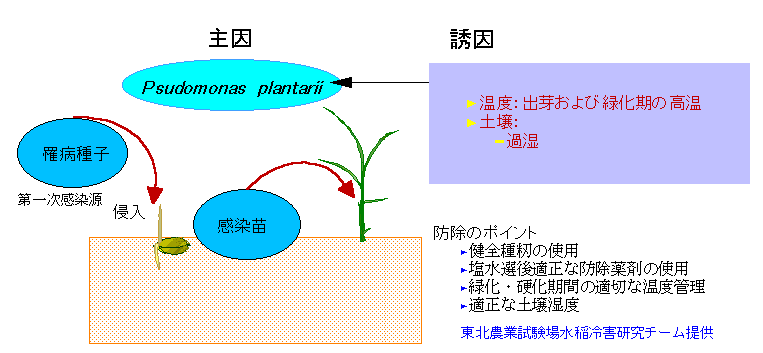



reigai@ml.affrc.go.jp