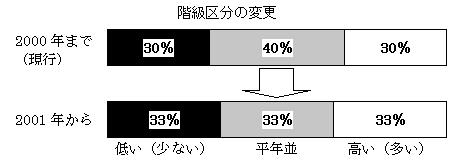図説:東北の稲作と冷害
2001年1月1日から平年値の更新と階級区分の変更
仙台管区気象台から、2001年1月1日から平年値を更新し、階級区分を変更するとのお知らせがありましたので、ここにご紹介します。
気温や降水量などの平年値を2001年1月に更新します。2001年1月1日以降は、1971年から2000年の30年間の平均値を平年値として使用します。
また、季節予報などで用いる階級区分の仕方を変更します。現行では、出現率がそれぞれ30%、40%、30%となるように決めていましたが、2001年からはこれらの出現率を33%の等確率とします。
1.平年値の更新
(1)平年値の更新
平年値は、気象(気温および湿度、降水量、日照時間など)や天候(猛暑および干天、多雨、寡照など)などを評価する基準として、防災気象情報をはじめ各種気象情報のなかで幅広く利用されるとともに、その場所や地域における気候を理解する指標として用いられています。
気象庁では、世界気象機関(WMO)の技術規則にもとづき、西暦年の末位が1の年から数えて0の年に終わる連続する30年間の気象資料の平均値を求め、それぞれの基準となる平年値として使用することを定めています。平年値は、気候の変動を考慮に入れることなどから、10年ごとに期間を新しくして再計算(更新)することにしています。1991年から2000年までは、1961年から1990年の平均値を平年値として使用してきましたが、2001年以降は、1971年から2000年の30年間の平均値を平年値として使用します。
(2)新平年値の概要
近年は気温の高い状態が目立っており、1990年代は高温となった年が集中しています。世界の年平均地上気温は、観測史上7位までの高温を記録した年がこの90年代に現れており、過去120年間のどの期間と比べても高い状態になっています。このような状況は日本でも同じような傾向で、この影響は新平年値にも現れています。
例えば1月の月平均気温を見てみると、青森の1961年から1990年の平年値は-1.8℃、1971年から2000年の新平年値は-1.4℃で、新平年値は0.4℃高くなっています。同様に、秋田は-0.4℃が-0.1℃、盛岡は-2.5℃が-2.1℃、山形は-0.9℃が-0.5℃、仙台は1.0℃が1.5℃、福島は1.1℃が1.4℃と、東北地方の各地では新平年値が0.3℃から0.5℃高くなっています。
2.階級区分の変更
(1)階級区分の変更
季節予報などでは気温や降水量などの平年からの偏りの程度を表現する場合、「低い(少ない)」、「平年並」、「高い(多い)」の3つの階級を用いています。現行では、これら階級の幅は出現率がそれぞれ30%、40%、30%となるように決めていましたが、2001年からはこれらの出現率を33%の等確率とします。なお、平年より極端に異なる状況を解説するために、下位10%、上位10%の出現率の範囲をそれぞれ「かなり低い(少ない)」、「かなり高い(多い)」として補足的に用いることにします。
(2)階級区分の変更の利点
季節予報で用いられる気温などの確率表現では、過去の気候の出現率(気候的出現率)を把握しておくことが重要です。現行の季節予報では各階級の気候的出現率が同じでないため確率表現を分かりにくくしていたようです。3つの階級の気候的出現率を等しくし、一般感覚に合わせることにより季節予報の確率表現が理解しやすくなります。
また、世界気象機関(WMO)の基礎組織委員会(CBS)などでは予測技術および予報結果を国際的に比較するための評価手法などが議論されています。この比較に利用される評価手法は等出現率階級区分が基本となっています。今回、日本も33%の等確率とすることによって、季節予報の国際的な比較が出来る様になり、予報技術の向上につながることが期待できます。なお、アメリカ(NOAA)では、平成7(1995)年頃に(30%、40%、30%)方式から等出現率階級区分に変更しました。
| 本件に対する問い合わせ |
| 仙台管区気象台技術部 |
| 気候・調査課 |
| (電話:022-297-8110) |



reigai@ml.affrc.go.jp