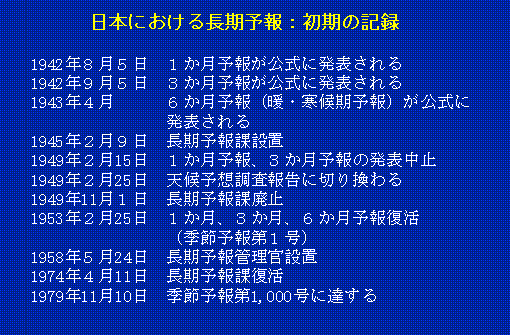図説:東北の稲作と冷害
長期予報の生い立ち
日本の長期予報の歴史は外日本の長期予報の歴史は外国と異なる。アメリカでは週間予報から1か月予報、そして3か月予報と進んだ。だが、日本の場合はまず、暖候期(4月〜9月)の天候を予想する季節予報の研究から長期予報が始まった。
日本の長期予報の研究は東北地方の冷害を何とか防ごうとする農民に対する愛情から出発した。明治凶作群と言われる大凶作が明治35年、38年、大正2年と相次いで東北地方をおそった。この凶作の惨状が契機となって、豊凶予知に農学者が取り組むようになった。常に農民の苦しみをうたった宮沢賢治の恩師旧盛岡高等農林学校の関豊太郎は“飢饉は海から来る”の俚諺(りげん:民間に行き渡っている通俗なことわざ)どおりに、寒流が春から優勢なことが冷害の原因であると指摘した。農事試験場の安藤広太郎もまた4月の気温、5月の水温とその時の気圧配置をみればおそくとも6月初めに、8月の低温が予報できるとした。注目すべきは、これら初期の研究は農学者によって進められた。
一方、気象学的な方面では、明治43年に岡田武松は北日本の冷夏は三陸沖に張り出すオホーツク海高気圧が原因であることを指摘した。さらに岡田は宮古など北日本各地の7〜8月気温と世界各地の気象要素との相関分析も行った。
もともと、社会の要望が予報技術より先行して始められた長期予報の研究だけに、大正2年の大凶作を境に豊作が続くようになると研究熱は急速にさめた。しかし、海洋とオホーツク海高気圧の重要性を指摘した成果は受け継がれ、再び凶作が続発し始めた昭和6年以降になって海洋観測のための観測船が配置され、岩手山などに測候所が新設された。
この時代には東京の中央気象台に研究室が設けられ、長期予報の研究が始まった。当時の仙台気象台長の指導で東北地方の全官署が協力して長期予報の研究を進めた。当時戦時下であり、長期予報を用い冷害を軽減することで国策に合致し研究が進められた。肌で農民に接し、農民の要望に応えようとしただけに研究には情熱がみなぎっていた。
このように、日本の長期予報は研究室の中から生まれたと言うよりは、現地で農民と接する現場の人たちによって育てられた。
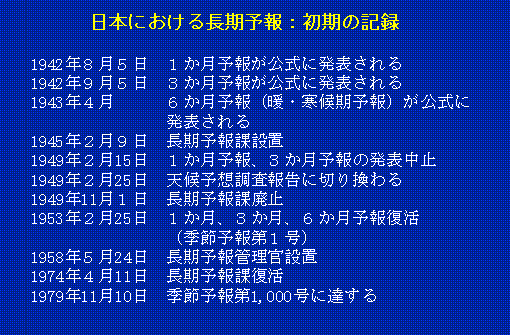
日本における長期予報の初期の歩みを図に示す。
(参考文献:根本順吉・朝倉 正.(1980)「気候変化・長期予報」(気候と人間シリーズ2)、朝倉書店)



reigai@ml.affrc.go.jp