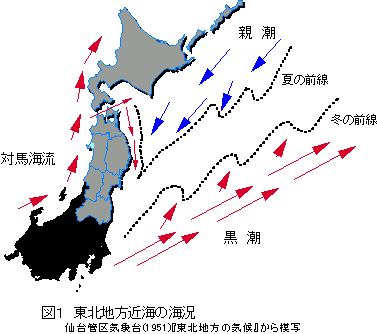図説:東北の稲作と冷害
東北地方における海況
古くから三陸沖の海水温が夏期の異常低温に関係することが知られていた。そこで仙台管区気象台(1951) 『東北地方の天候』の"東北地方における海況:海流(福田喜代志著)"を基に、当時の気象関係者の海水温に関する考え方を顧みる。
東北地方における海況
東北地方近海の海流は極めて錯綜している。特に、三陸沖は3種の海流があって、これらの海流の消長は東北地方の気候にも影響して、夏期の凶冷的気候(異常低温)の原因となるともいわれている。海流の特徴は次の通り(図1参照)。
- 黒 潮:黒潮の主流は台湾の東方沖を北上し、紀州、房総半島を洗って北東に流れ、関東地方の東方沖より東に去り、太平洋を横断して北米大陸西岸に至り、その末尾は南下して、さらに赤道地帯を西進して、再び黒潮を構成する環太平洋流の主要部分である。
- 対馬海流:黒潮本流が東シナ海を流れるときに、その一部が北上して日本海に入り対馬海流を構成する。対馬海流は東北地方西海岸を洗って北上し、宗谷海峡に至るが、その一部は津軽海峡に入り、下北半島を回って南下して、三陸沿岸の近海約20海里以内を流れ次第に衰弱するか金華山沖付近に至ることもある。
- 親 潮:千島海流ともいわれ、千島付近より北海道南方に流れ、東北地方の東方沖で津軽海流と黒潮に接触するが、その海表面の位置は季節的にもまた年によっても異なる。黒潮に接触した親潮は密度の関係で、黒潮の下層に潜り込んで南進を続ける。親潮の温度は表面では、3,4月に最低となり三陸沖では3℃程度、8月末に最高になり20℃程度になる。
黒潮と親潮の境は季節により変動し、普通の年ならば春に親潮が最も南下し、福島県の東方沖に達する。初秋までは黒潮が北上して、青森県東方沖または北海道近海に及ぶこともある。この状態も年によって異なり、黒潮や親潮が接岸する場合や黒潮の北上が活発でない年もある。三陸沖の海況は著しい相違がみられ、特に夏期において著しい。この違いは親潮の動きにもよるが、それとともに黒潮の北上の強弱によるためである。明治44年〜昭和16年間の東経143度、北緯39度の表面温度の平年差の変化をみると、10か月の周期で変化しているとともに、7年位の周期が見いだせる。この変化は夏期東北地方の異常低温に緊密な関係がある。
大正2年、昭和6,9,10,16年は東北地方の夏期の気温は異常に低温であったが、水温も著しい低温が続いた。ただし、大正7,9年、昭和1,2年では水温は低い状態が続いたが、夏期の異常低温はみられなかった。このことから、東北地方に凶冷をもたらすような夏期には水温は低いが、水温が低い場合には必ず気温も低いとは限らない。三陸沖水温は東北地方の夏期低温の重要な指針ではあるが、気温は水温だけでは予測できない。



reigai@ml.affrc.go.jp