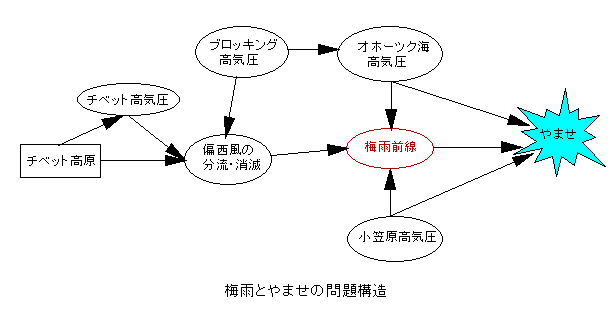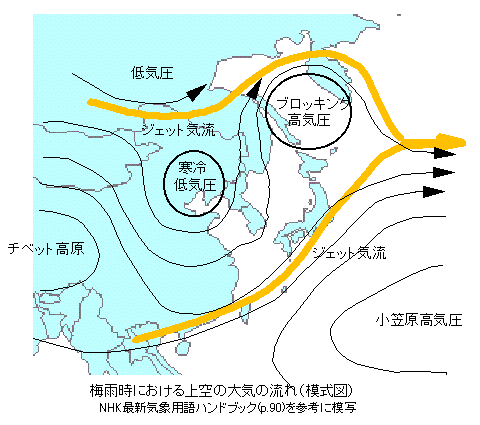図説:東北の稲作と冷害
梅雨
梅雨と台風は、日本では古くから水田の水供給源として重要な役割を担ってきている。しかし、この梅雨は東北地域では冷害の直接的原因となるオホーツク海高気圧から吹き込む“やませ”の消長と密接に関係する。
梅雨
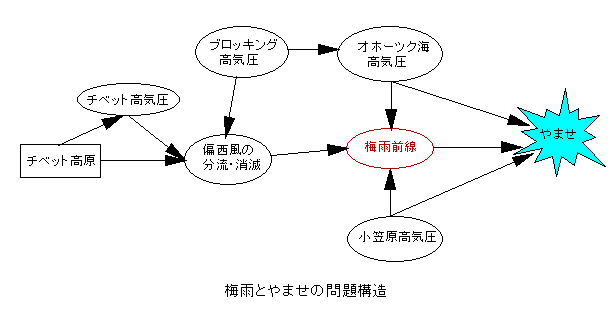 梅雨とは、春から夏へ気候が変わるとき、日本、中国、韓国など東アジアの地域だけにみられる雨期をいう。日本では、秋霖とならぶ長雨の季節である。梅雨は中国由来の言葉であり、揚子江流域で、梅の実が熟す頃に降る雨なので梅雨といわれた。日本では昔からこの雨を五月雨(さみだれ)といったが、「梅雨」を“つゆ”と読むようになったのは、「日本歳時記」(貞享4年、1687年)に記載されていることから、江戸時代といわれる。
梅雨とは、春から夏へ気候が変わるとき、日本、中国、韓国など東アジアの地域だけにみられる雨期をいう。日本では、秋霖とならぶ長雨の季節である。梅雨は中国由来の言葉であり、揚子江流域で、梅の実が熟す頃に降る雨なので梅雨といわれた。日本では昔からこの雨を五月雨(さみだれ)といったが、「梅雨」を“つゆ”と読むようになったのは、「日本歳時記」(貞享4年、1687年)に記載されていることから、江戸時代といわれる。
梅雨は地域によってその現れ方に大きな差があり、次のように4つの期間に分けられる。
第1期:5月中旬から下旬のはしり梅雨の頃。中国の華南方面から南西諸島にかけて梅雨前線が現れて、この地域が入梅する。
第2期:6月上旬から中旬の頃。梅雨前線が本州の南岸沿いに停滞し、西日本から東日本にかけて入梅する。
第3期:6月下旬から7月上旬の頃。梅雨前線が本州上に停滞して、梅雨が最盛期を迎え、局地的な大雨が起こりやすい。
第4期:7月中旬から下旬の頃。梅雨前線が北上して、関東以西では梅雨明けとなるが、北日本では、梅雨末期の大雨が起こりやすい。
ふつう第2期と第3期の間には、一時的な晴天の続く梅雨の中休みがある。
梅雨前線は小笠原高気圧とオホーツク海高気圧の境を、数千キロにわたって東西にのびる前線で、ほぼ40日かかって本州を北上する。梅雨前線の北側は、オホーツク海高気圧からの冷たい北よりの風が吹いており、南側は小笠原高気圧から暖かい湿った南よりの風が吹いている。これら2つの気流が、前線付近に集まって上昇気流ができるため、雲が発生し、雨を降らせる。梅雨前線が日本付近に停滞するのは、前線の両側にある高気圧の勢力がほぼ釣り合っているためである。
梅雨期の高層における大気の流れを模式的に示すと下図のようになる。
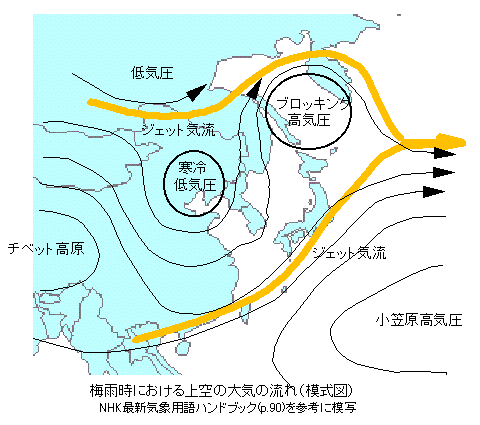 季節の移り変わりにつれて北上した偏西風のジェット気流は、6月にはチベット高原付近を通るようになる。高原の影響で南北に分流していたジェット気流は、日本の東海上で再び合流する。このうち日本の南を走るジェット気流が梅雨に関係が深いとされている。
季節の移り変わりにつれて北上した偏西風のジェット気流は、6月にはチベット高原付近を通るようになる。高原の影響で南北に分流していたジェット気流は、日本の東海上で再び合流する。このうち日本の南を走るジェット気流が梅雨に関係が深いとされている。
大陸東部からオホーツク海にかけては、偏西風の流れが大きく蛇行して、中国東北部には冷たい寒冷低気圧があり、オホーツク海にはブロッキング高気圧がある。このような大気の流れは長続きするので、地上の天気図ではオホーツク海高気圧が勢力を保ちながら停滞する。この高気圧圏内の空気は、水温の低い海面に接しているため、地表付近から冷やされて下層の気温が低くなる。
夏に向かうにつれ、チベット高原上の大気が熱せられて高温となるため、上空にチベット高気圧ができる。これとほぼ同時に、高原の南側を走るジェット気流が消滅し、北側の気流だけが残る。こうなると、オホーツク海高気圧は消滅し、日本は小笠原高気圧に覆われて梅雨明けとなる。
東北地域における梅雨入りと明けの時期は、次の通りである。
(1) 平年の梅雨入りの時期
東北南部:6月12日頃、東北北部:6月14日頃
(2) 平年の梅雨明けの時期
東北南部:7月23日頃、東北北部:7月26日頃
参考文献:
日本放送協会編集(1987)「NHK最新気象用語ハンドブック」、日本放送出版会。



reigai@ml.affrc.go.jp