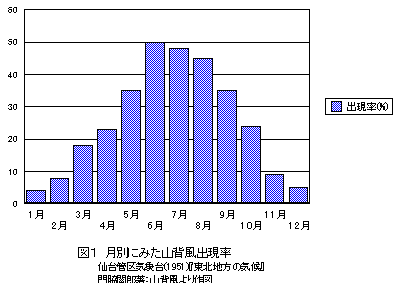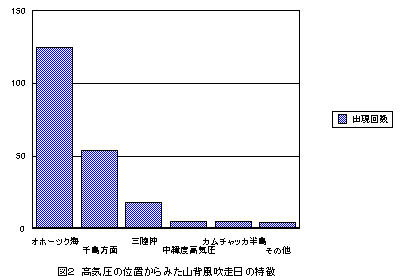図説:東北の稲作と冷害
山背風
餓死風または凶作風と呼ばれるほど恐れられている山背風(ヤマセ)について、仙台管区気象台(1951) 『東北地方の天候』の"特殊気候:山背風(門脇關郎著)"を基に、当時の気象関係者のヤマセの特徴に対する考え方を顧みる。
山背風
三陸沿岸地方では東よりの風のことを"山背風(ヤマセ)"と呼んでいるが、夏期の山背風は低温をもたらすため、別名餓死風または凶作風と呼ばれるほどである。山背風については、岡田の気象学には北東風で寒冷雨気を含んで凶作を起こしやすいと述べている程度である。山背風に関する詳しい解析を八戸の資料(昭和12年〜23年)によって夏期(5月〜8月)について行った。
1) 山背風の風向:風向別気温偏差合計{(風向別気温偏差)x(出現回数)}を求めると、低温と高温の風向が判然と分かれる。すなわち、低温は東を中心とする「東−南南東」の風向に、高温は「南−西」の風向にまとまっている。したがって、一般に低温をもたらす山背風とは、東を中心とする「東−南南東」の風全体を指しているといえる。
2) 気温偏差と出現状況:月別にみると、7月が最も低温の偏差が大きいのがわかる。山背風の年間の各月の出現率(%)を求めると図1の通りである。6,7,8月がその最盛期であり、冬期は非常に少ない。また、山背風の連続性をみると、3日ないし7日連続する傾向がある。
3) 連続日数と気温:山背風の連続日数の長いことは、一方では山背風の勢力が強いとも考えられる。連続日数と気温偏差をみると、連続日数が長いような山背風ほど、低温の程度が強い。連続日数が4日以下の場合は気温偏差が-1℃程度であるが、4日以上では-3℃程度で、連続日数4日を境として急に変化している。
4) 山背風吹走日の気象状況:一日中山背風の吹走した日を求めると、期間中211日あった。この211日について気温、降水量、雲量、日照、湿度、霧日数の各階級ごとの出現頻度を求めて山背風の特徴をみると、次のようにいえる。すなわち、"曇天で日照はなく、湿度が多く気温は低く(平均より3℃低い)、降雨および霧を伴った陰気な天気が多い。"各要素の階級別の出現頻度は以下の通りである。
- 気温偏差:頻度の極大は-3℃のところにあり、大体左右対称の分布を示す。
- 降水量:降水皆無は18%で、80%以上は降水がある。
- 雲量:曇り、晴れ、快晴の出現頻度はそれぞれ88、10、2%である。
- 日照時間:不照の出現頻度は54%である。
- 湿度: 86〜100%の間に一様に分布する。
- 霧日数: 96%は薄霧以上が発生している。
5) 山背風吹走日の気圧配置:山背風吹走日211日について高気圧の位置によって分類して、その出現回数をみると図2の通りとなる。このように、山背風が吹走する場合には、オホーツク海および千島方面に高気圧がある場合が9割程度を占める。したがって、山背風はオホーツク海気団の流入の一現象と考えられる。



reigai@ml.affrc.go.jp