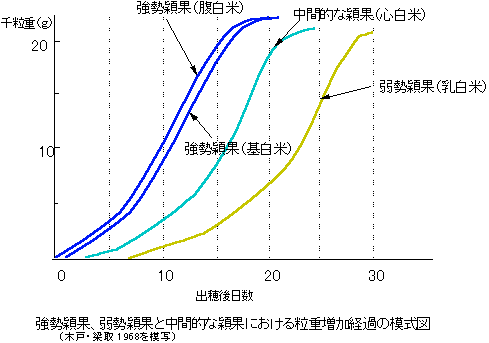図説:東北の稲作と冷害
強勢穎花、弱勢穎花と玄米の粒質との関係
腹白米、基白米、心白米、乳白米が1穂のどのような位置に発生しやすいかを調べ、それらの発生機構について穎花の開花順序との関係を考察する。またこれら粒質と発生危険期との関係を検討する。
強勢穎花、弱勢穎花と玄米の粒質との関係
この実験は水稲品種「越しみのり」を用いて、一次枝梗数が10本の穂を100本選び、1粒ずつ粒質と穎花の着生位置を調べたものです。腹白米、基白米、心白米、乳白米がその種類により穂上の特定位置に発生し易いということが分かれば、開花順序との関係が明らかになり、その発生機構を考える重要な手がかりになります。
得られた観察結果は次の通りです。
1)腹白米
腹白米は開花の早い強勢穎花に多く発生します。一次枝梗の最先端の穎花(第1粒)については、最も上の枝梗で発生率が高く、下位のものほど発生率が低くなる傾向がみられます。次に、各一次枝梗の頂部の穎花から下に数えて第4,5粒についてみると、中部から下部の一次枝梗では頂部穎花より多く発生する傾向がみられます。このことはこれら一次枝梗では頂部の第1粒の粒重より第4,5粒の粒重の方が大きくなることと関係するようです。また下部の穂首に近い一次枝梗では、これら腹白米が発生する位置の穎花は腹白米ではなく乳白米の発生率が高くなる傾向があります。
2)基白米
基白米は上部一次枝梗の第2,3粒に多く発生します。この位置は一次枝梗中で開花の遅い位置ですが、上部一次枝梗に多くみられることが重要な特徴といえます。基白米は外観上完全米に近く、また葉緑素の残っているものがほとんどみられないことからも、穂全体としては割合早い時期に開花したものであることを示唆します。中央部一次枝梗以下ではこの位置には乳白米の発生率が高くなります。
3)心白米
心白米は中央部一次枝梗の2次枝梗に多く発生する傾向があり、腹白米との発生位置は明らかに異なります。(注:ただ、別の研究者は両者は同じ位置に発生する傾向を認めています。この違いは使用した品種の違いなどが影響したものと考えられます。)
4)乳白米
乳白米は下部一次枝梗に明らかに多い傾向があり、特に2次枝梗の第2,3粒に多い特徴があります。この位置は1穂の中でも最も開花の遅い弱勢穎花であり、乳白米の中には青米が多く含まれることがあります。
以上の観察結果に基づいて、それぞれの米粒の発育過程を考えてみることにします。
腹白米を早く開花した穎花の特に発育のよいもの、基白米を強勢穎花の中ではやや遅く開花したもの、心白米を中間的な穎花でやや遅いもの、乳白米を開花の遅い弱勢穎花と仮定して、それぞれの開花時期のずれと玄米の発育速度の特徴を考えると次のように図示できます。
図にあるように、弱勢穎花は強勢穎花に比べると次のような特徴を示します。
○開花時期が遅れる。
○初期より発育が遅れる。
○発育が緩慢で後期まで発育を続ける。
○完熟まで要する日数が長い。
○粒重が小さい。
中間的な穎花は両者の中間的な発育をたどると考えられます。
このように、強勢穎花、中間的な穎花、弱勢穎花の発育過程には互いに重複がみられ、これが澱粉転流に関して相互の競合関係となり、その程度と米粒発育過程における時期の違いにより、種々の形態の不透明部分を形成するものと考えられています。
したがって、適正な籾数の確保、稲体の健全性の長期維持、不良環境に対する適切な技術対応がこれらの障害回避に不可欠となります。
さて上の仮説を基に各種玄米粒質の発生危険期を考えることにします。
・腹白米:腹部細胞にデンプン蓄積不足が生ずる腹白米は、登熟後期の胚乳組織内の転流通路で、腹部が最も遠い末端にあることが原因とも考えられています。これも転流は正常でも、蓄積側の生長しすぎが引き起こす現象ともみられます。これらを上の図と関連づけると、出穂後0〜10日頃における胚乳細胞の分裂程度と出穂後10〜20日頃の高温によって腹白米の発生は助長されるものとみられます。
・基白米:登熟の最後の充実がわずかに不十分となり、澱粉集積が停止した粒といえます。上の図と関連づけると、出穂後10〜20日頃が養分集積の後期となるため、この時期の高温によって発生が助長されるとみることができます。
・心白米:初期に胚乳細胞の容積拡大が旺盛に過ぎて、転流が正常なのに中心部の細胞を一杯にすることができない現象とも考えられています。これらを上の図と関連づけると、出穂後0〜10日頃における胚乳細胞の分裂程度と出穂後5〜15日頃の高温によって心白米の発生は助長されるものとみられます。
・乳白米:玄米の成熟途中で一時的に養分集積が抑えられた場合に、その時充実すべき部位が白色不透明で残り外見上乳白色なるもので、初期の養分集積不良が原因です。上の図と関連づけると、出穂後10〜20日頃がその時期に相当し、この時期の高温が発生を助長すると考えることができます。
以上のように、高温で特徴的に発生する背白米に関する知見はここでは得られませんが、これら品質を劣化させる粒質は出穂後0〜20日頃が危険期ということができます。早期警戒システムで用いている玄米発育段階では、危険期は出穂期から糊熟期に相当します。(なお、出穂期から乳熟期の高温が玄米の胚乳組織の過剰な生長を促すという点に関しては文献調査中です。)
参考文献
・木戸三夫・梁取昭三(1968):腹白、基白、心白状乳白、乳白米の穂上における着粒位置と不透明部のかたちに関する研究。日作紀37:534-538.



reigai@ml.affrc.go.jp