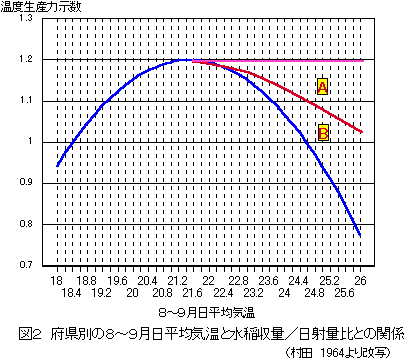図説:東北の稲作と冷害
水稲収量の地域性に関係する日射と温度
わが国における水稲収量の地域性を通して、登熟期間の日射と温度が収量に及ぼす影響を検討し、高温による生理的障害の概要を把握する。
水稲収量の地域性に関係する日射と温度
わが国における水稲収量は、一般に東北・北陸・信越地方で高く、西南暖地で低い傾向にあることが古くから知られています。このことは図1に示すように、1999年産水稲の都道府県別収量分布にもその特徴を見ることができます。さて、この地域性は何に原因するのか。
まず、玄米の炭水化物は出穂前の茎葉に蓄積されていたもの(出穂前約10日間)と出穂後に新たに同化されたもの(出穂後30日間)とから作られます。そこで、全国の普通期水稲作を通してみると、8,9月の気象条件がこの期間と大きく関係すると考えられます。そこで、この期間の日射量、平均気温と都道府県別収量を解析したところ、次の諸点が明らかになりました。
①日射量と収量との関係は全体で見るとほとんど関係がない。しかし北海道、東北、北陸、長野など、比較的気温の低い地方に限ると、日射量が多いほど収量が高くなる傾向がある。
②平均気温と収量との関係では、21,22度付近に最大値を示し、それより気温が低くてもまた高くても収量は低下する傾向がある。
次に、日射量の影響は常に正比例的に働くと仮定して、収量を日射量で割った値と平均気温との関係を求めたところ、図2のような21.5度付近に極大値をもつ放物線の関係が描けます。これにより水稲収量の地域性がかなりはっきりと表せます。
上の模式図から最適な登熟温度域からさらに高温条件になると、どのような生理的な変化が起こるか。次の2つが主な原因と考えられています。
1.高温による光合成と呼吸のバランスが悪くなること。すなわち呼吸によるロスが大きくなることです。それを図中[A]の領域で示しています。
2.高温に伴う植物体の老化や根の障害による光合成能力の低下と葉面積の減少により総光合成量が低下することです。それを図中[B]の領域で示しています。
このように、最適な登熟気温21.5度を上回り始めると、呼吸によるロスがまず直接的に影響を及ぼします。温度がさらに上がると、2.の間接的なものが大きく影響し始め、それが総光合成量を減少し、呼吸のロスと相まって玄米の生長に大きく影響を及ぼすことになります。
このことは水稲収量の地域性を概説ものですが、最適な登熟温度にある東北地方では高温年には同様の生理的な影響を受けると考えられます。また登熟温度が高くなると、上の生理的な変化によって登熟不良に伴う玄米の粒質にも影響が現れます。
参考文献
・村田吉男(1964)、わが国の水稲収量の地域性に及ぼす日射と温度の影響について。日作紀33巻、59-63。



reigai@ml.affrc.go.jp