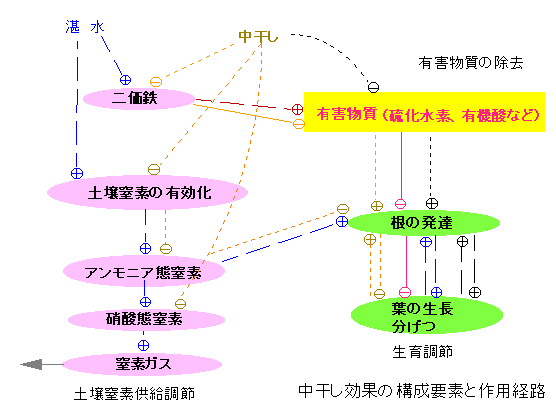図説:東北の稲作と冷害
中干しの効果
中干しの作用機構はやや複雑であるが、主に関連する土壌と稲の要素と作用経路を概説する。
中干しの効果
中干しの効果に関係する主な要素と作用経路を下図に示す。プラスの経路は増加あるいは促進効果を、マイナスの経路は減少あるいは抑制効果を示す。経路の色分けは作用の引き金となる要素が異なることを示す。
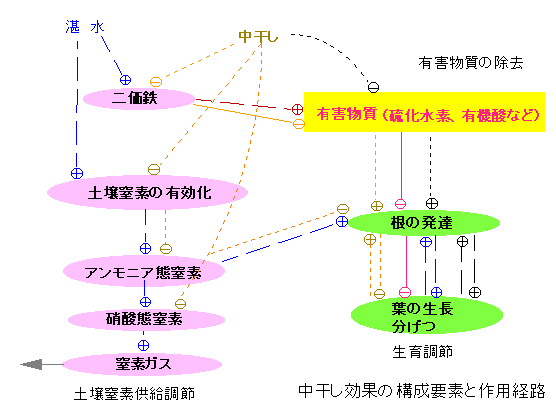 まず、湛水の効果(図説:「湛水された水田土壌の特徴と窒素の動き」参照)は、土壌窒素の発現を促進し、水稲の生育に好適な環境を作る。また同時に、土壌溶液中の2価鉄濃度が上昇する。この作用経路を青で示す。
まず、湛水の効果(図説:「湛水された水田土壌の特徴と窒素の動き」参照)は、土壌窒素の発現を促進し、水稲の生育に好適な環境を作る。また同時に、土壌溶液中の2価鉄濃度が上昇する。この作用経路を青で示す。
湛水を長期間継続したり、水温の高い状態が続いたりすると、硫化水素や有機酸などの有害物質が土壌中に徐々に蓄積される。これらは根の発達に悪影響を及ぼし、養分吸収を阻害し、葉の生長や分げつ形成を抑制する。この作用経路を赤で示す。
中干しは、次のような大きく2つの作用経路をもつ。
(1) 中干しにより土壌窒素の発現を一時的に抑制し、稲の生育を調節する作用。
(2) 2価鉄濃度を低下させ、また酸素の供給によって有害物質を無毒化し、その後の稲の生育を良好にする。
このように、中干しに関係する要素は多く、またその作用経路も複雑である。
また、中干しの効果は、草姿の制御、倒伏防止、土壌状態の改変を通して生育後期に現れるため、顕著な効果を認めにくい。しかし重要な基本技術である。
なお、中干しの効果には、このような稲の生育コントロールの他に、地耐力の向上が図られ、収穫機械の運行を容易にするなどの作業上のメリットも大きい。
参照図説:



reigai@ml.affrc.go.jp