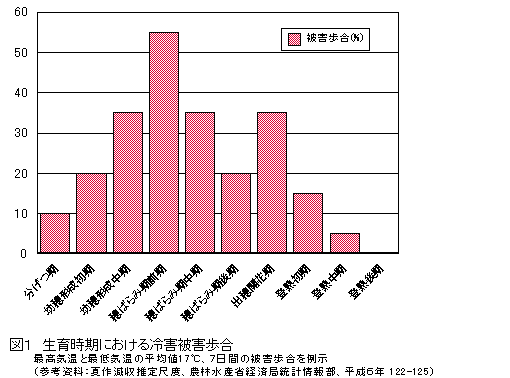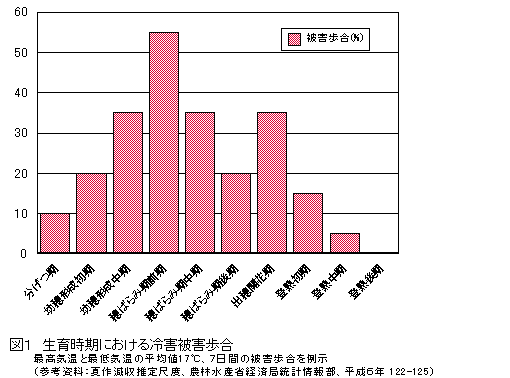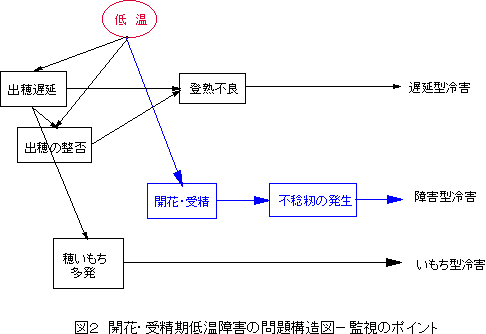気象被害監視のポイント
開花・受精期低温障害の問題構造
開花・受精期において低温に長期間遭遇すると、とるべき対策技術はほとんどなく不稔籾が多発する。他には出穂遅延による生育遅延と穂いもちの多発が懸念される。葉いもち多発地帯では穂いもち防除の徹底は欠かせない。
開花・受精期は冷害研究の初期では低温による不稔籾発生の最大の危険期とされていた。その後の研究で低温による不稔籾発生の最大の危険期は減数分裂期(厳密には小胞子初期)であることが明らかにされた。しかしながら、開花・受精期はそれについで低温に弱い時期であることは次の点からも理解できよう。まず、低温が被害歩合に及ぼす程度を生育時期別に比較した図1をみる。これは『夏作減収推定尺度−冷害(1)』にあるものである。それぞれの生育時期は次のように定義されている。分げつ期は6月上旬〜7月中旬、幼穂形成期初期は出穂期前30〜25日、幼穂形成期中期は出穂期前25〜15日、穂ばらみ期前期は出穂期前15〜10日、穂ばらみ期中期は出穂期前10〜5日、穂ばらみ期後期は出穂期前5〜0日、出穂開花期は出穂期後0〜5日、登熟初期は出穂期後5〜10日、登熟中期は出穂期後10〜25日、登熟後期は9月上旬〜10月上旬。
このように、出穂・開花期は穂ばらみ期前期(減数分裂期)に次いで低温に弱い時期である。その理由としては、一般に生殖細胞の形成を終わった頴花は、開花機能が活動的になるにしたがい、低温障害を受けやすくなるといわれる。
開花・受精期低温障害の問題構造を図2に示す。このように視点を広げてみると、問題は3点ある。①低温による出穂遅延や出穂の整否は登熟不良につながり、特に作付可能期間を最大限利用しているような地域では遅延型冷害を起こす可能性が高くなること。②低温の直接的な影響による不稔籾の発生である。これが多発すると障害型冷害となる。③低温による出穂遅延が起こる場合は天候が一般的には不順である。葉いもちが多発している場合、穂いもちの防除が適期にできないことが多く、穂いもちが多発する可能性が高まる。その場合はいもち型冷害となることもある。このようにみると、やはり出穂・開花・受精期は低温に伴う被害を最も警戒すべき時期といえよう。
次に、監視のポイントを低温による開花・受精障害に限定して考えると、次のような障害の特徴がある。
①成熟して開花準備の整った花粉が障害を受けやすいこと。すなわち通常の開花時間(午前10時頃が盛期)に低温に遭遇すると被害の程度が大きくなる。それゆえ、開花と最高気温との関係が高いといわれる。
②17℃程度の比較的弱い低温でも7日以上の長期に曝されると、不稔籾が多発すること。
③不稔籾を発生させる限界温度は品種間で異なり、17.5〜23.5℃の6℃程度の差異があること。
④日射量が不足するような場合には、限界温度が上がり不稔籾の発生を助長すること。
警戒に際しては、田中(1962)の次の研究成果(表1)を参考に気温指標と警戒メッシュを作成する。
表1 開花温度と不稔歩合との関係
| 気温の適否 | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 平均気温(℃) | 不稔歩合(%) |
|---|
| 最適温 | 29.5〜32.5 | 19.5〜22.5 | 24.5〜27.5 | 3〜7 |
|---|
| 適 温 | 27.5〜29.5 | 17.5〜19.5 | 22.5〜24.5 | 7〜12 |
|---|
| やや適温 | 24.5〜27.5 | 14.5〜17.5 | 19.5〜22.5 | 12〜25 |
|---|
| やや不適温 | 21.5〜24.5 | 10.5〜14.5 | 16.0〜19.5 | 25〜50 |
|---|
| 不適温 | 18.5〜21.5 | 7.5〜10.5 | 13.0〜16.0 | 50〜85 |
|---|
| 全く不適 | 18.5以下 | 7.5以下 | 13.0以下 | 85以上 |
|---|
<気温指標と警戒メッシュの設定>
(1)深水管理の必要な地域の移り変わり:幼穂形成期間に平均気温が20℃以下になると、低温障害が発生しやすくなる。そこで、20℃を限界気温として、深水管理の必要な地域を特定する。この気温指標は前7日間の移動平均値で図示する。
(2)低温の程度を測る冷却量の移り変わり:冷却量は(日平均気温−20℃)で得られる指標である。この値が負でかつ数値が大きいほど低温の程度が大きくなり、幼穂形成期間においては低温被害が大きくなると推定される。この気温指標は前7日間の移動平均値で図示する。
(3)極端な最低気温の移り変わり:低温障害の発生の基準温度として、最低気温17℃が一般によく使われます。それを基に、極端な低温が来た地域の移り変わりを、最低気温の前3日の移動平均値で図示する。
(4)開花・受精に不適な最高気温の移り変わり:開花・受精期は低温に弱い時期です。文献等を参考に開花・受精に不適な地域の移り変わりを、最高気温を用いて前5日間の移動平均値で図示する。
(5)開花・受精期の警戒メッシュ:上の表を参考にして、警戒メッシュの気温区分は次のように設定する。(基準温度は幼穂発育期間のものと同一に設定。)
- 平均気温17℃以下:かなりの受精障害が予想される。
- 平均気温17℃〜20℃:受精障害が懸念される。
- 平均気温20〜22℃:受精障害が心配される。
- 平均気温22℃以上:被害は予想されない。
なお、平均気温は前7日間の移動平均で示す。




reigai@ml.affrc.go.jp