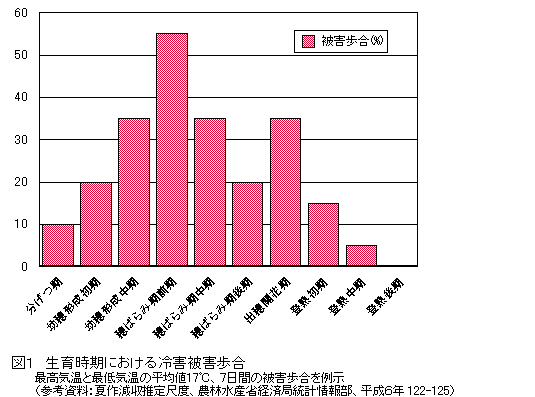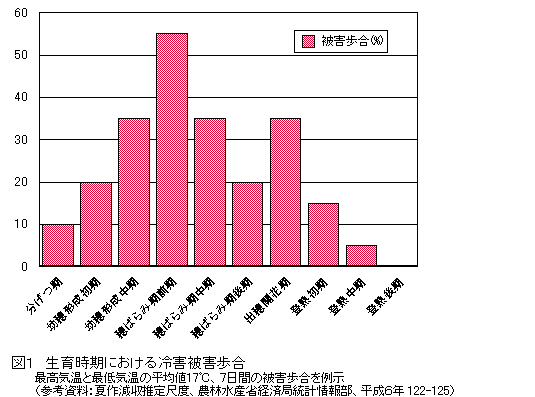婥徾旐奞娔帇偺億僀儞僩
搊弉婜掅壏忈奞偺栤戣峔憿
丂搊弉婜偼廂検惉棫夁掱偐傜傒傞偲丄偙偺帪婜偺娐嫬偺椙斲偵傛偭偰搊弉曕崌偲愮棻廳偑嵟傕塭嬁傪庴偗傞丅偦偟偰丄偙傟傜偺梫慺偑寛傑傞搊弉廔婜偵側傞偲廂検偑妋掕偡傞丅偙偺帪婜偺掅壏偵懳偟偰偼丄昦奞拵杊彍埲奜偺懳嶔媄弍偼傎偲傫偳側偄丅傑偢丄掅壏偑旐奞曕崌偵媦傏偡掱搙傪惗堢帪婜暿偵斾妑偟偨恾侾傪傒傞丅偙傟偼亀壞嶌尭廂悇掕広搙亅椻奞(1)亁偵偁傞傕偺偱偁傞丅偦傟偧傟偺惗堢帪婜偼師偺傛偆偵掕媊偝傟偰偄傞丅暘偘偮婜偼俇寧忋弡乣俈寧拞弡丄梒曚宍惉婜弶婜偼弌曚婜慜俁侽乣俀俆擔丄梒曚宍惉婜拞婜偼弌曚婜慜俀俆乣侾俆擔丄曚偽傜傒婜慜婜偼弌曚婜慜侾俆乣侾侽擔丄曚偽傜傒婜拞婜偼弌曚婜慜侾侽乣俆擔丄曚偽傜傒婜屻婜偼弌曚婜慜俆乣侽擔丄弌曚奐壴婜偼弌曚婜屻侽乣俆擔丄搊弉弶婜偼弌曚婜屻俆乣侾侽擔丄搊弉拞婜偼弌曚婜屻侾侽乣俀俆擔丄搊弉屻婜偼俋寧忋弡乣侾侽寧忋弡丅偙偺傛偆偵丄搊弉偺弶婜傎偳掅壏忈奞傪庴偗傗偡偔丄屻婜偵側傞偲傎偲傫偳掅壏偺塭嬁偑側偔側傞丅偨偩偟丄掅壏偵傛偭偰惗堢偑抶墑偟偰廂妌偑偱偒側偔側傞抶墑宆椻奞偺婋尟惈偼巆傞丅
丂搊弉婜掅壏忈奞偺栤戣峔憿傪恾俀偵帵偡丅偙偺傛偆偵帇揰傪峀偘偰傒傞偲丄娭學偡傞栤戣偼俀揰偁傞丅嘆搊弉曕崌傪寛掕偡傞彅梫慺偲丄嘇愮棻廳傪寛掕偡傞彅梫慺偲偱偁傞丅偙傟傜偼摉慠側偑傜惗堢偺慜楌偵塭嬁偝傟傞丅嵟傕戝偒偔塭嬁偡傞傕偺偼丄搊弉婜埲慜偵寛傑傞侾姅曚悢偲侾曚栢悢偲偱嶼弌偝傟傞扨埵柺愊摉偨傝偺憤栢悢偱偁傞丅棫抧娐嫬傗嵧攟懱宯偵墳偠偨揔惓側栢悢傪妋曐偡傞偙偲偑婎杮偱偁傞丅師偼丄尭悢暘楐婜偲弌曚丒奐壴婜偵偍偄偰掅壏偵憳嬾偟偨応崌偵惗偠傞晄庴惛栢偺敪惗偱偁傞丅傑偨掅壏偵敽偆惗堢抶墑偼丄廐椻傑偱偵惓忢側尯暷偑廂妌偱偒傞偐偳偆偐偵娭學偡傞丅弌曚丒奐壴婜偺掅壏偵傛偭偰惗偠傞弌曚偺晄懙偄傕宱尡揑偵搊弉晄椙偵側傞応崌偑懡偄丅傕偆堦偮偼偄傕偪昦偱偁傞丅梩偄傕偪偑忋埵梩偵懡敪偟偰偄傞応崌偵偼丄曚偄傕偪傊偺恑揥偑寽擮偝傟傞丅偙傟傜梫慺偲搊弉婜娫偺婥壏偲擔幩検偼搊弉曕崌偲愮棻廳偺寛掕偵戝偒偔學傢傞丅偟偨偑偭偰丄偙偺暋嶨側宯偵婥徾揑側忈奞偑婲偙傞偐偳偆偐傪娔帇偡傞偙偲偼丄旕忢偵擄偟偄丅
丂搊弉曕崌偲愮棻廳傪捈愙揑偵娔帇偡傞偙偲偼偱偒側偄丅偦偙偱丄娔帇偺億僀儞僩偼丄嘆尯暷偺敪堢偑弴挷偵悇堏偡傞偐偳偆偐丅嘇嬌抂側婥壏悇堏偵傛偭偰崅壏忈奞傗掅壏忈奞偑敪惗偡傞偐偳偆偐偵偁傞丅嘆偵偮偄偰偼丄尯暷偺敪堢梊應忣曬偵偁傞傛偆偵丄暯嬒婥壏偺悇堏偐傜偁傞掱搙梊應偑壜擻偱偁傞丅抶墑宆椻奞偺婋尟惈偑偳偺抧堟偵偁傞偐丅孹曚婜丄屝弉婜丄墿弉婜丄偦偟偰惉弉婜傊偲恑傓宱夁偑丄埨慡嶌婜忣曬偵偁傞岲揔側敪堢宱夁偐傜偳偺掱搙偢傟偰偄傞偐傪娔帇偡傞偙偲偱壜擻偲側傞丅嘇偵偮偄偰偼丄暯惉俇丆侾侾丆侾俀擭偺崅壏搊弉偵傛傞尯暷昳幙偺楎壔偑娔帇偡傞忋偱廳梫偲側傞丅
丂偦偙偱丄寈夲偵嵺偟偰偼丄師偺傛偆側婥壏巜昗偲寈夲儊僢僔儏傪嶌惉偡傞丅
亙婥壏巜昗偲寈夲儊僢僔儏偺愝掕亜
(1) 嬌抂側嵟掅婥壏偺堏傝曄傢傝丗搊弉掆巭偑寽擮偝傟傞嵟掅婥壏偲偟偰丄敧桍(1960)偼侾侽亷傪愝掕偟偰偄傞丅偦傟傪婎偵丄嬌抂側掅壏偑棃偨抧堟偺堏傝曄傢傝傪丄嵟掅婥壏偺慜俁擔偺堏摦暯嬒抣偱恾帵偡傞丅
(2)暯嬒婥壏偵傛傞崅壏忈奞婋尟抧堟偺堏傝曄傢傝丗暯惉俇丆侾侾丆侾俀擭偺俁擭娫偵偍偗傞娔帇宱尡偐傜婥壏嬫暘傪愝掕偡傞丅暯嬒婥壏俀俈亷埲忋偼婋尟搙偑崅偄丄俀俇乣俀俈亷偼寈夲偑昁梫偱偁傞丅偙偺婥壏巜昗偼慜俈擔娫偺堏摦暯嬒抣偱恾帵偡傞丅
(3)嵟掅婥壏偵傛傞崅壏忈奞婋尟抧堟偺堏傝曄傢傝丗搊弉曕崌偵戝偒偔忈奞傪梌偊傞嵟掅婥壏偲偟偰丄徏搰丒妏揷(1959)偼俀俁亷傪愝掕偟偰偄傞丅偦傟傪婎偵搊弉曕崌偵晄棙側嵟掅婥壏偺堏傝曄傢傝傪慜俈擔娫偺堏摦暯嬒抣偱恾帵偡傞丅
(4)搊弉婜掅壏忈奞寈夲儊僢僔儏丗婥壏偑彊乆偵掅壓偡傞帪婜側偺偱丄婜娫偺慜敿偲屻敿偲偱偼堎側傞偲悇掕偝傟傞偑丄恾侾側傜傃偵懠偺尋媶惉壥傪嶲峫偵偟偰丄寈夲儊僢僔儏偺婥壏嬫暘偼師偺傛偆偵愝掕偡傞丅
- 暯嬒婥壏侾俈亷埲壓丗惗堢抶墑偑偐側傝寽擮偝傟傞丅
- 暯嬒婥壏侾俈亷乣侾俋亷丗惗堢抶墑偑寽擮偝傟傞丅
- 暯嬒婥壏侾俋乣俀侾亷丗惗堢抶墑偑怱攝偝傟傞丅
- 暯嬒婥壏俀侾亷埲忋丗惗堢抶墑偼梊憐偝傟側偄丅
丂側偍丄暯嬒婥壏偼慜俈擔娫偺堏摦暯嬒偱帵偡丅
丂




丂
reigai@ml.affrc.go.jp