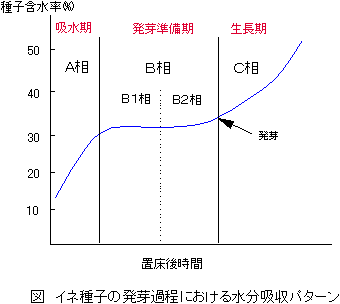図説:東北の稲作と冷害
浸種・催芽
苗の出芽遅延や不揃いは、催芽の不十分や不揃いによることが少なくない。均一なハト胸状態の催芽籾を得るのが種子の予措の目的で、良い種籾を使用し、浸種・催芽を正しく行う必要がある。
浸種・催芽
浸種は催芽の前段階として種籾に吸水させる過程である。イネの種籾は風乾重の15%の水分を吸ったことから胚の発芽活動が始まる。すべての種籾をそれまで吸水させるのが目的である。
種子の水分吸収過程は3つの生理相に区分される(高橋1962:下図参照)。
A相は物理的な吸水過程であり、吸水期といえる。B相は吸水増加は停滞するが、発芽のための実質的な物質代謝が進行する発芽準備期である。この期間はさらに2相に分けられる。B1相は胚の生長を規制する代謝系が関与する時期。B2相は炭水化物代謝がもっぱら行われる時期であり、この相が完了すると発芽が起こる。またC相は発芽後、幼芽と幼根が活発に生長する時期である。
浸種には、吸水は行われるが発芽活動が始められない低温、すなわち約13℃以下で行うのが理想的である。10〜13℃ではふつう6〜7日を要する。実際には、寒冷地を除いて、浸種時期に13℃以下の低温は得られないので、15℃で5日、20℃では3〜4日程度が目安となる。
浸種の後期になると、温度が高い場合は呼吸作用が高まり、炭酸ガスや有機酸が発生し、また酸素が不足するので水換えが必要である。
催芽は充分吸水した種籾に胚の生長に最適の温度を与え、芽を出させることである。催芽程度は、幼根・幼芽が1mmでる、いわゆるハト胸程度が適する。催芽温度は32℃が最適で、発芽速度、発芽歩合、発芽揃いともに優れる。32℃ではハト胸までにほぼ24時間を要する。
<参考資料>
・星川清親(1980):『新編食用作物』.養賢堂.115頁.
・高橋成人(1962):稲種子の発芽に関する生理遺伝学的研究。東北大農研彙報8:91-115.



reigai@ml.affrc.go.jp