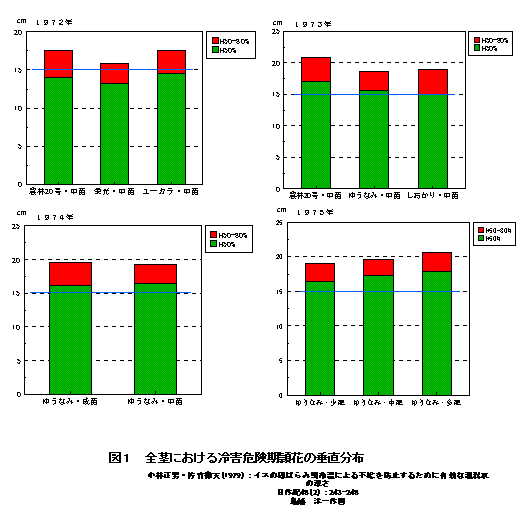図説:東北の稲作と冷害
深水灌漑
深水灌漑の水深:17〜20cm目標
東北地域水稲安定生産連絡協議会の席上,東北農業試験場西山岩男次長が冷温感受性の最も高い時期は通常減数分裂期と言われているが,厳密には’小胞子初期’であると指摘された.事実,作物学等の教科書にはそのように記載されています.このことは周知のところであり,減数分裂期と小胞子初期との日数の差は数日であるために圃場レベルでは実用上問題とならないために慣用されてきました.
西山次長の指摘の背景には,大きくは次の2点があります.すなわち,
(1)学術的に明らかにされている事実はそれを尊重して,用語等は適切に使用し,今後の研究はこの知見を基礎に発展されるべきであること.
(2)危険期の冷温の対応技術として,減数分裂期の深水灌漑(15cm程度)が指導されているが,厳密な意味での小胞子初期を適用した場合に,15cm水深では不十分であることが明らかにされている.
西山次長は特に(2)の重要性を強調します.この根拠として,次の論文を紹介します.この実験結果と結論は1970年代に北海道で北海道の品種で得られたものであることをお断りしておきます.
小林正男・佐竹徹夫(1979):
イネの穂ばらみ期冷温による不稔を防止するために有効な灌漑水の深さ.日作紀48(2):243-248
酒井(1949)が減数分裂期と小胞子期の頴花の80%以上が地面上12〜15cmまでの高さに分布することを明らかにし,その後穂ばらみ期深水灌漑では水深を15cmに保つことが指導されてきた.
西山ら(1969)は穂ばらみ期に冷気温下で温水深水灌漑処理で,水深14cm以下の水深では不稔を全く防止できず,水深21cmでは完全に防止できた.
そこで,本報告では圃場栽培イネの全茎を対象として小胞子初期頴花の垂直分布を調べ,深水灌漑における有効水深を再検討した.
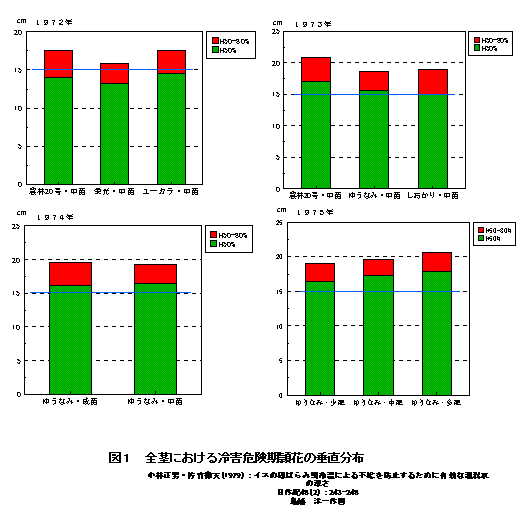
実験方法:
実験年度:1972-73年
供試品種:農林20号,栄光,ユーカラ,ゆうなみ,しおかり
処理:苗質,栽植密度,施肥量
調査:幼穂形成期の数日後から出穂期までの間,毎日サンプリング.節位別葉耳間長を測定.葉耳間長 -10cm〜+6cmの茎について幼穂を固定,地面上2cmごとの高さ別に頴花を分級.花粉発育時期をアセトカーミン染色によるスメア法で検鏡し,4分子期と小胞子前期を冷害危険期として,危険期頴花の出現数を調べた.
実験結果:
1.全茎における冷害危険期頴花の垂直分布
危険期頴花の出現期間は農林20号では11〜14日,他の品種では6〜8日.
危険期頴花は地面上6〜34cmに分布し,12〜18cmにモードがある.累積頻度が50(H50%)%,80(H50%+H50-80%)%の高さは図1の通り.
.累積頻度80%は15.9cm〜20.8cm,累積頻度50%は13.2cm〜17.9cm,最小値と最大値の間には4〜5cmの差がある.
これらの高さは品種,施肥量で異なるが,苗質では差はほとんどない.
2.節位別分げつにおける冷害危険期頴花の垂直分布
危険期頴花の垂直分布は節位別分げつ間に明瞭な差がみられる.たとえば,1973年の農林20号を例に取ると,次の通り.
| | 分布範囲 | 累積頻度80% |
| 主 稈 | 14-34cm | 25.6cm |
| 5号分げつ(一次) | 12-30cm | 21.6cm |
| 51号分げつ(二次) | 10-22cm | 17.4cm |
このように,発生順序の遅い分げつの累積頻度80%高さは早いものに比較して低い.
結 論:
従来言われていた深水灌漑の水深12〜15cmでは,せいぜい危険期頴花の50%程度しか含まれない.
西山らの実験において水深14cmで全く効果が認められなかったのは,危険期頴花の分布位置の高い主稈のみを用いたためと思われる.
水温が畦間気温を上昇させる効果に関する過去の知見を考慮しても,穂ばらみ期の深水灌漑実施に当たっては,危険期頴花の少なくとも80%以上が位置する高さまで灌水することを原則とし,17〜20cmの水深を目標とすべきである.



reigai@ml.affrc.go.jp