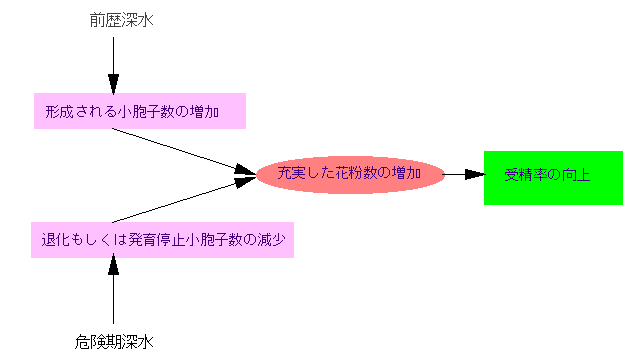図説:東北の稲作と冷害
深水管理の障害不稔回避メカニズム
前歴深水と危険期深水はそれぞれ不稔発生を回避する機構は異なるが、いずれも充実花粉数を増加させる効果をもち、それにより受精が良好となることを概説する。
深水管理の障害不稔回避メカニズム
前歴深水と危険期深水を組み合わせることで、障害不稔の発生が著しく軽減できることは、図説:前歴深水と危険期深水の組み合わせ効果で概説した。
では、なぜそのような障害不稔回避効果があるのかを下図で説明する。
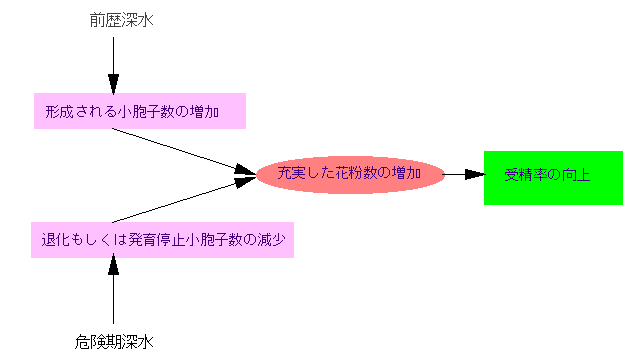 まず、前歴深水管理の実施要領は次の通りである。
まず、前歴深水管理の実施要領は次の通りである。
○ 幼穂形成期(幼穂長約 2mm)から危険期初めまでの水深を10cmに保つ。この期間の幼穂が水面下に位置するようにする。また幼穂の発育に合わせて段階的に水深を増しても良い。
○ 水温25度を目標にできるだけ水温上昇を図る。
前歴水温の上昇による受精率の向上は充実花粉数の増加に起因すると考えられている。充実花粉数は、減数分裂によって形成される小胞子数と小胞子から花粉に発育する途中で退化もしくは発育停止した小胞子数の差によって決まる。
前歴深水管理によって水温を高く保持することは、減数分裂によって形成される小胞子数を増加する効果をもち、これにより充実花粉数が多くなる。
次に、危険期深水管理の実施要領は次の通りである。
○ 出穂前10〜11前を中心とする数日の間(減数分裂期の危険期)に気温が限界以下に下がったとき、水深を17〜20cmに保ち、幼穂を水面下に位置するようにする。
○ このときの水温の限界温度は耐冷性の弱い品種では19〜21度、強い品種では17〜19度といわれる。
危険期に深水にして水温を高く保持すると、退化または発育停止する小胞子数を少なくし、充実花粉数を増加させる効果がある。
このように、前歴深水と危険期深水とは、花粉の形成に関与することは同じでも、作用機構は異なる。いずれも充実した花粉数を増やす効果をもつ。このことが受精に良好に働き、不稔の発生を軽減するといわれている。したがって、両深水管理を組み合わせると、それぞれの単独で実施した以上の効果が期待できる。
特に、前歴深水は水深が10cm程度で良いので、実施しやすく冷害防止効果も大きいので、冷害対策の基本技術として位置づけられよう。
参考資料:
佐竹徹夫ら(1995) 「前歴深水灌漑による冷害防止」『イネ冷害克服をめざして』記録集。東北農業試験場。
参照図説:



reigai@ml.affrc.go.jp