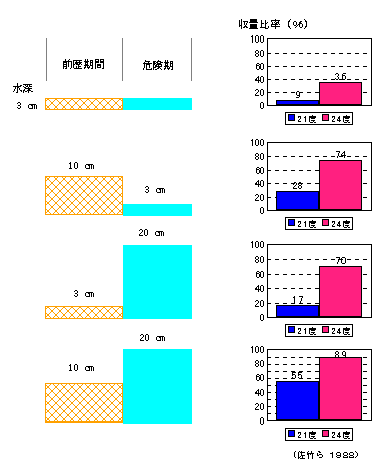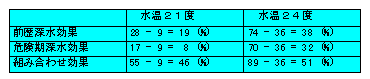図説:東北の稲作と冷害
前歴深水と危険期深水の組み合わせ効果
前歴深水管理と危険期深水管理を組み合わせて実施することによって、障害型冷害回避効果が著しく高められることを概説する。
前歴深水と危険期深水の組み合わせ効果
減数分裂期の危険期に深水管理すると、障害不稔の発生が軽減されることは古くから知られていた。
ここでは前歴深水と危険期深水のそれぞれの単独効果と、2つを組み合わせた効果、さらには水温の高低でそれらの効果がどのように変化するかについて説明する。
下図は前歴深水管理を提唱した佐竹徹夫氏らの研究成果の一部である。品種は北海道の「キタヒカリ」。この実験では、前歴期間の気温18度、水深(3cm, 10cm)と危険期の水温18度、水深(3cm, 20cm)に変え、それらを組み合わせて処理し、危険期に冷気温15度5日間さらし、収量と収量構成要素を調べたものである。収量比率は無処理区(気温:昼間26度、夜間19度)に対する百分率で示す。
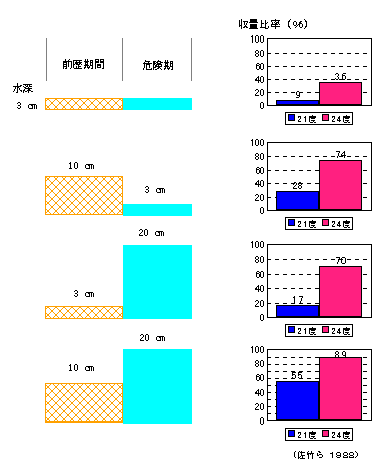 まず、前歴と危険期の深水の単独効果をみる。水温21度条件下では前歴深水の収量比率は28%、それに対して危険期深水のそれは17%である。次に水温24度条件下では、同様に74%と70%となる。
まず、前歴と危険期の深水の単独効果をみる。水温21度条件下では前歴深水の収量比率は28%、それに対して危険期深水のそれは17%である。次に水温24度条件下では、同様に74%と70%となる。
このように低水温条件下では、前歴深水の効果の方が危険期のそれよりも大きいことが分かる。
次に、両深水を組み合わせたときの効果をみる。水温21度条件下では収量比率は55%、水温24度条件下では89%となる。
このように両深水管理を組み合わせると、減収程度が大幅に改善でき、その効果は水温が低い場合に顕著に現れる。
前歴深水と危険期深水の単独効果と組み合わせ効果を数値でみると、次の通りである。
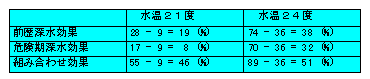 低水温条件下では、前歴と危険期の深水の効果を加えたものよりも、組み合わせたときの効果がはるかに大きい。
低水温条件下では、前歴と危険期の深水の効果を加えたものよりも、組み合わせたときの効果がはるかに大きい。
以上の結果からも分かるように、幼穂形成期から出穂期まで長期に低温が予想される場合には、この2つの水管理技術を組み合わせて障害型冷害を軽減することが大切である。
参考資料:
佐竹徹夫ら(1988) 「新水管理法による冷害防止」日本作物学会紀事 57(1):234-241.
参照図説:
質 問:前歴深水と危険期深水の障害型冷害回避メカニズムは?



reigai@ml.affrc.go.jp