|
図3-4は、仙台管区気象台が1996年9月1日から1999年8月31日までに発表した1か月予報の向こう1か月の平均気温について、横軸に予報した確率、縦軸に予報した階級が出現した比率を示したもので、グラフ中の数字は発表回数を示している。 発表回数の少ない60%などを除いて棒グラフはほぼ対角線上にのっている。このことは、予報した階級が、予報した確率におおむね対応して出現していることを示している。 たとえば、確率50%という予報は延べ118回発表されており、それに対する予報した階級の出現率は45%、確率20%という予報は延べ112回発表されており、それに対する予報した階級の出現率は16%となっている。このように、確率は予報した階級のおおよその出現率と考えることができる。 |
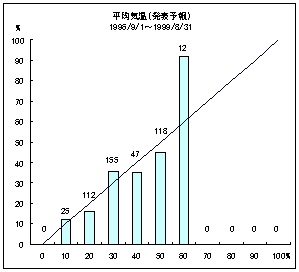
|
|
図3-4 1か月予報における気温確率の出現率 縦軸は予報した気温階級が出現した比率(%)、横軸は予報した気温確率(%)、グラフ中の数字は発表回数を示す。 | |
|
1か月予報の向こう1か月の平均気温の確率予報を、主に農家が冷害による減収を軽減させるための対策に利用する場合を考える。 対象農家は、先に策定した8つの冷害危険度地帯区分にそれぞれ属する農家とする。水稲作付面積は1haとし、収入は地帯平均収量(kg/10a)と政府買入価格16,000円/60kgから算出する。なお、平成10年産米穀の政府買入価格は、米価審議会の審議を経て、現行16,217円から改定後15,805円(水稲うるち玄米、1〜5類1・2等平均包装費込み、生産者手取予定価格60kg当たり)に決定されている(食糧庁の米価審議会「10年産米の政府買入価格・米穀の標準売渡価格」より)。 冷害等による被害額は、1972年〜1998年までの収量変動を考慮して設定する。図3-5は東北農業試験場による冷害危険度地帯区分の地帯1における収量推移だが、この期間においては年次に伴う収量の著しい増加は認められない。他の地帯も同様(図略)で、冷害等による被害量は収量の標準偏差を指標とする。 |
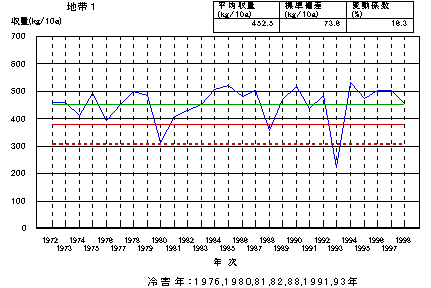
|
|
図3-5 冷害危険度地帯区分別の収量推移(東北農業試験場による) 冷害危険度地帯区分の地帯1における収量推移で、縦軸は10a当たりの地帯平均収量、横軸は年次を示す。 | |
| 地帯区分 | 被害1 | 被害2 | 被害3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収量 | 被害量 | 収量 | 被害量 | 1993年被害量 | ||
| 1 | 462 | 58 | 453 | 74 | 238 | |
| 2 | 599 | 54 | 588 | 78 | 300 | |
| 3 | 545 | 37 | 542 | 41 | 96 | |
| 4 | 527 | 62 | 494 | 132 | 475 | |
| 5 | 594 | 34 | 594 | 34 | 63 | |
| 6 | 402 | 69 | 377 | 112 | 354 | |
| 7 | 511 | 49 | 500 | 73 | 283 | |
| 8 | 430 | 88 | 398 | 141 | 429 | |
| 地帯区分 | 収入 | 被害1 | 被害2 | 被害3 | 被害1の除外年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 15.5 | 19.7 | 63.5 | 1993年 |
| 2 | 160 | 14.4 | 20.8 | 80.0 | 1993年 |
| 3 | 145 | 9.9 | 10.9 | 25.6 | 1993年 |
| 4 | 141 | 16.5 | 35.2 | 126.7 | 1980、1993年 |
| 5 | 158 | 9.1 | 9.1 | 16.8 | − |
| 6 | 107 | 18.4 | 29.9 | 94.4 | 1980、1993年 |
| 7 | 136 | 13.1 | 19.5 | 75.5 | 1993年 |
| 8 | 115 | 23.5 | 37.6 | 114.4 | 1980、1993年 |
| 地帯区分 | 被害1 | 被害2 | 被害3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 25 | 8 |
| 2 | 35 | 24 | 6 |
| 3 | 51 | 46 | 20 |
| 4 | 30 | 14 | 4 |
| 5 | 55 | 55 | 30 |
| 6 | 27 | 17 | 5 |
| 7 | 38 | 26 | 7 |
| 8 | 21 | 13 | 4 |